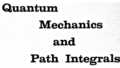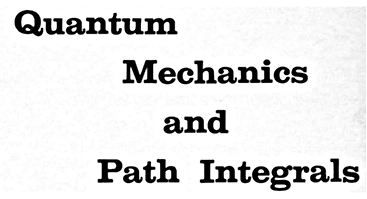
\(\)
Problem 6-25
It has been argued that the equations of the electrodynamics must, like those of mechanics, be converted to a quantized form on the basis of the photoelectric effect. Here an electron of energy \(\hbar\omega\) is occasionally emitted from a thin layer of metal under the influence of light of frequency \(\omega\). Is this impossible if matter obeys the quantum laws but light is still represented as a continuous wave? What arguments can you adduce for the necessity of giving up a classical description of electrodynamics, in view of the results of Prob. 6-24?
(解答) この問題は,「D.Bohm の第2章の文章」を抜粋することで解答に代えることにする.
光電効果
「光電効果」の実験は, 光または紫外線で照らされた金属の表面から電子が放出されること (電子には, 表面より中に入った層から解放されて来たものもある.そのような電子は金属を透過しなければならないのでその分だけエネルギーを失っている), また, 電子の運動エネルギーは輻射の強さには関係しないが, 輻射の振動数にだけは次式のように関係することを示すものであった:
\def\mb#1{\mathbf{#1}}
\frac{1}{2}mv^{2}=\hbar\omega – W
\tag{1}
\end{equation}
ここで \(\omega=2\pi\nu\) は入射する輻射の角振動数であり, \(W\) は金属の「仕事関数」すなわち, 金属内部から電子を取り出すのに必要なエネルギーである.Einstein こそが, この結果を Planck の仮説と関係付けた最初の人であった(1905年). ~~ 以下略す~~.
光電効果に於いて, どんな事が起こるのかを古典的に説明することを考えてみる.輻射が原子内で振動している一個の電子に当たったとすると, 輻射は電子にエネルギーを与える.電場が原子内の電子の振動数と共鳴するような振動数で振動しているとすると, 電子は原子から解放されるまで光波からエネルギーを吸収する.原子の性質が「電子は \(h\nu=\hbar\omega\) に等しい量を得るまで, エネルギーを吸収し続け, エネルギー獲得後, 外に放出されるという風のものである」と仮定すれば, 光電効果を説明できるだろうと思える.ところが, 原子がそういう性質を持っているとすると,「非常に弱い光では, 光電効果は長時間のあいだ観測されない」に相違ない.必要なエネルギーの素量を貯えるのに長い時間が掛かるからである.
【 補助メモ 】 調和振動している束縛電子に輻射が当たると, 前述のブログ記事の結果式 (11) から, 次のようなエネルギー転移がなされるのであった:
\Delta \mathcal{E} = \frac{\pi e^{2}}{m}\big|\mb{E}(\omega_{0})\big|^{2}
\tag{2}
\end{equation}
この時, 入射光波の電場 \(\mb{E}=\mb{E}_{0}\sin\omega t\) の振幅 \(\mb{E}_{0}\) は任意の大きさを取ることが出来る.従って,入射光波の強度を非常に小さくしてやれば, エネルギー転移は幾らでも小さくすることが可能である.よってその場合, 入射光波からのエネルギー転移 \(\Delta\mathcal{E}\) が \(\hbar\omega\) 以上になる時間まで, 電子は放出されないことになる.
ところが, 金属の粉末粒子と極めて弱い光を使って実験してみると, 金属塵の粒子は \(h\nu\) のエネルギーを貯えるには長時間掛かる程少量であったのに, それでも, 瞬時に現れる光電子が見られたのである.この結果を説明するには, その金属が多様なエネルギーを持った電子を含んでいたのだと考えれば良い.すると, 金属に光を当てたとき, 直に適当なエネルギーの 2, 3 の電子が解放され得る.ところが, \(h\nu\gg W\) の場合を考えると,「そんなにも多くの余分のエネルギーを持つ電子が, 丁度その場合に適合する振動数の光波で解放され始めるまで金属内に無期限に留まっているということ」は有りそうに思えない.その上, どのようにして金属から一個の電子を解放しようとするかということとは関係なく (例えば, 金属を陽子で爆撃するか, 或いは他の電子で爆撃するかに関わりなく), ともかく常に同一の仕事関数 \(W\) に等しい最小エネルギーを与えてやらなければならない事が分かっているのである.同様に, 電離ポテンシャル \(I\) に等しい一定の最小エネルギーを与えなければ, 気体原子から電子を解放出来ない事 (Franck-Hertz の実験), 更にそのとき, ある電子は \(h\nu-I\) に等しい運動エネルギーを持つ気体原子から極めて弱い光で瞬時に飛び出して来る事が分かった.それ故, これらの証拠一切から見ると,「ある電子が, それが持って逃げ出すエネルギーと略同じエネルギーを最初から持っていたのだ」と仮定して光電効果を説明する可能性は, 排除されなければならなくなる.~~以下略す~~.
電磁輻射の散乱
電子による光波の散乱の古典的な説明を考えて見る.古典論に従うと, 入射光波は振動する電場 \(\mb{E}=\mb{E}_0 \sin \omega t\) を作り, この電場によって電子は振動運動を始め, 入って来る輻射の方向と直交する平面に対称的に輻射を出すことになる.その結果, 輻射される全運動量はゼロである.それ故, 光のこの部分によって運ばれる入射ビームから失われた運動量は, 電子に行かねばならない.これは電子に輻射圧を及ぼし, 電子を加速する.電子に及ぼされる輻射の正味の力の大きさを知るには, 強さ \(I\) (\(\mathrm{erg/cm}^{2}\) 秒で表される) の入射ビームから散乱されて出るエネルギーの割合に対して Thomson が導いた公式を使えば良い.その結果は次である:
\frac{dW}{dt}=\frac{8\pi e^{4}}{3m^{2}c^{4}}I
\tag{2}
\end{equation}
【 補助メモ 】 「Thomson の公式」については, 前に書いたブログ記事:「電磁波の放射について」の中の式 (48)で示してある:
\sigma_{T}=\frac{\bar{I}}{S}=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2},\quad
S=|\mb{S}|=\frac{c}{4\pi}\big|\mb{E}\big|^{2}=I
\end{equation}
この式では, 入射ビームの強さ \(I\) は「エネルギーの流れ」を表わすポインティング・ベクトルの大きさ \(S\) で表されていた.ポインティング・ベクトルの大きさ \(S=|\mb{S}|\) は「単位面積を単位時間に通過する場のエネルギーの大きさだった」からである.上式の \(S\) は平面波の場合である.また \(\bar{I}\) は散乱によって単位時間に放出されるエネルギー量の時間平均であるから, それは式 (2) の \(dW/dt\) に相当する.また, もし電子が原子に束縛されて調和振動子と見做される場合には次となる:
\frac{dW}{dt}=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}
\frac{\omega^{4}}{(\omega_{0}^{2}-\omega^{2})^{2}+\omega^{2}\gamma^{2}}I
\tag{2′}
\end{equation}
ビームから吸収される運動量は \(W/c\) であるから, 電子は次の割合で運動量を得ることになる:
\frac{dp}{dt}=\frac{1}{c}\frac{dW}{dt}=\frac{8}{3}\frac{\pi e^{4}}{m^{2}c^{5}}I
\tag{3}
\end{equation}
この輻射圧を生じる機構のもっと直接的な描像を得るには, \(x\) 方向に電場を, \(y\) 方向に磁場を持って \(z\) 方向に入射する光波を考えると良い.それにより電子には \(-e\mb{E}-(e/c)\mb{v}\times\mb{H}\) の力が働くのであるが, 磁気的な力は無視できる.それは真空中では \(|\mb{E}|=|\mb{H}|\) であるため, \(\mb{v}/c\) を含む項は電子が光速に近い速さで運動するのでなければ, 電子の運動には小さな効果しか生じないからである.従って \(v/c\ll 1\) の場合はそれを摂動として考慮に入れればよい.電子に働く電気的な力は, 一周期について時間平均するとゼロになるが, 磁気的な力の \(z\) 成分の時間平均はゼロではない.計算してみるとそれが式 (3) で与えられる値に等しいことが分かる.
電子が速くなるに連れて, その結果として低振動方向への「Doppler 変移」が生じる.この変移は2つの部分に於いて現れる.第一に, 電子が光のビームから隔たると, 入射光より低い振動数の場の遭遇することになる.次に輻射を出す過程に於いて他の Doppler 変移が入って来る.それは第一の効果を前方向に於いて相殺し, 後方向に於いては倍加するものである.事実, Doppler 変移の角度に対する依存性は丁度, Compton 効果に対する式で与えられる事が示される.それは前のブログから次である:
\lambda-\lambda_{0}\simeq \frac{2W}{mc^{2}}\lambda_{0}\sin^{2}\frac{\phi}{2}
\tag{4}
\end{equation}
古典論からすると,「この Doppler 変移は, 粒子がエネルギーを得るに連れて, 時間と共に次第次第に増えて行くであろう」.その上, 粒子がどんな大きさのエネルギーでも貰うことが出来るから,「輻射の強さ或いは露出の時間を変えて行くと, Doppler 変移のあらゆる可能な値が, 与えられた角度に於いて観測され得る」に相違ない.ところが, 実験的には, 輻射の強さや露出の時間とは無関係に, 波長のズレのただ一つの値だけが観測されるに過ぎないことが見出されている. こういった事柄は, エネルギーや運動量をやり取りする過程が古典論で予言されるような連続的なものではなく, 量子論が示唆するように不可分なものであることを示している.
【 補助メモ 】 前のブログ記事の式 (23) から, 角振動数の表現で表わすならば次となる:
\omega-\omega_{0}=-\omega\frac{2v}{c}\sin^{2}\frac{\phi}{2}\quad \rightarrow\quad
\hbar\omega-\hbar\omega_{0}=-\hbar\omega \frac{2v}{c}\sin^{2}\frac{\phi}{2}
\tag{5}
\end{equation}
従って, 光を古典的な連続波として表現した場合, 問題 6-24 のエネルギー遷移の式 \(E_{final}=E_{initial}\pm \hbar\omega\) に相当するのは次式となる:
E_{final}=E_{initial} – \hbar\omega \frac{2v}{c}\sin^{2}\frac{\phi}{2}
\tag{6}
\end{equation}
【 参考 】 朝永先生の本の§ 12 にも「光電効果」についての記述があるので紹介しておこう.
「実験的には, 光線や紫外線或いはもっと振動数の高いX線を金属のような物質の表面に当てると, そこから電子が飛び出すことが知れれている. これを「光電効果」と名付ける. この現象は19世紀の終わり頃から知られていたのであるが, 20世紀に入ってレナート (Lenard) によって詳しく研究された.
Lenard が実験的に確かめたのは次の点である:
- 飛び出る電子一つ一つのエネルギーを測って見ると, それは照らす輻射線の強さに無関係であって,
- 照らす輻射線の強さを大きくすると, 飛び出る電子の個数 (詳しく言うと, 単位時間当たりの個数, すなわち頻度) が多くなるだけである. そして
- 飛び出る電子一つ一つのエネルギーは, 照らす輻射線の色に関係する. すなわち, その輻射線の波長が短い程, エネルギーの大きな電子が飛び出して来る.
この3つの実験事実を光の波動説によって説明することは極めて困難である. すなわち, 飛び出る電子のエネルギーが入射する輻射から得られるものとすれば, よほど変わったカラクリを考えない以上, このエネルギーは, 輻射が強ければ強いほど大きいことが予期される. すなわち, このとき原子内で起こる現象を想像してみると, 次のようなものとなるだろう. 原子内には電子が何か弾性力のようなもので結び付けられていて振動しているであろう. そこに光の波が入射すると, 電子はこの波に共振する. そうすると, 電子はエネルギーを光の波から貰って, 次第に大きな振幅で振動するようになる. そして最後に原子の外に, すなわち弾性力の勢力範囲の外に飛び出す. これが光電効果のときに見出される電子である. このように考えると, 光電効果で飛び出す電子のエネルギーは, 光の波に揺すぶられて原子の外に飛び出る前の最後の一周期乃至は半周期の間に光から貰ったものだと言うことになる (それ以前の沢山の周期の間に得たエネルギーは, 原子内で振幅が大きくなるのに費やされる). ところで, この最後の周期の間に得るエネルギーは, もちろん光の振幅が大きい程大きい. これは Lenard の見出した第1の事実に反するのみならず, 飛び出る電子のエネルギーの大きさから見ても非常に具合が悪い考えである. すなわち, Lenard は通常のアーク灯の光を用いて, 飛び出る電子のエネルギーが \(5\times 10^{-12}\) エルグ程度であることを確かめているが, これだけのエネルギーを1周期や2周期の間に電子が得るのは, とても強い光を用いなくては不可能である. こういう訳で, Lenard はその実験事実の理論的解釈については何かもっと複雑なカラクリを考えなければなるまいと結論した.