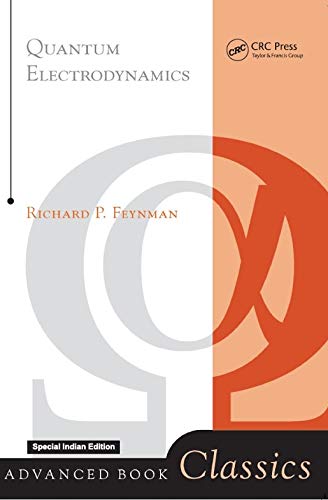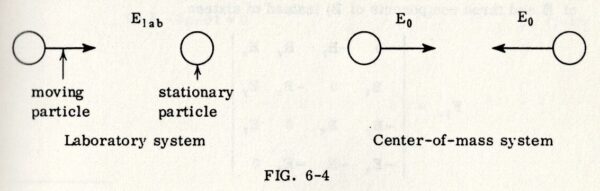特殊相対性理論の原理と結果の要約
相対性の原理とは, 関係する全ての物体が一緒に一様な速度
なぜなら, ニュートンの法則に含まれているのは2階微分だけだからである.しかし, マクスウェル方程式はこの変換を受けると変化し, この分野の初期の研究者はこの特徴を利用して地球の速度の絶対決定を試みた(マイケルソン-モーリー実験).しかしこの種の効果を検出できなかったため, 最終的にアインシュタインは「マクスウェル方程式はどの座標系でも同じ形であり, 特に光の速度はどの座標系でも同じである」という仮説を立てた.マクスウェル方程式を不変にする座標系間の変換は, 次のローレンツ変換である:
ただし
式の後半の形は, 座標軸の回転の式
との類似性を示すために書いたものである.連続した変換
であるならば, それは同じ最終系を与えるという意味である [2][訳註] 最初の式は, 相対論的な速度の合成則
ローレンツ変換の興味深い結果は,「動いている系では時計の針が遅く見える」ことである.ある座標系から別の座標系への変換には「テンソル解析」を使うと便利である.この目的のために
次の量は
「不変量」(invariant)とは, ローレンツ変換の下で変化しない量をいう.もし
和の記号を書かないようにするため, 以下のような「和の規則」(summation convenction)を使用する.すなわち「同じ添字が2回出現する場合は, 第1, 第2, 第3成分の前にマイナス符号を付けて和をとる」.「連続方程式」(continuity equation)のローレンツ不変性は, 4-ベクトル
ある系で電荷が保存される場合, すべての系で電荷が保存されるのは, この「積」である4次元の発散
ただし
興味深いことに, 自由粒子の波動関数
式 (2.7.12) に式 (2.7.9-a) を代入すると,
電磁気学の方程式
ただし
このテンソルは反対称 (
マックスウェル方程式の第2の組は, 4-ベクトルの表現で次のように書かれる:
ただし
ポテンシャル
しかしながら, ポテンシャル
ここで
これは便利な式である.なぜなら
この式は次の「波動方程式」であることが分かる:
式 (2.7.21-a) は, 時には次のスカラー演算子である「ダランベール演算子」:
を用いて次のように書かれる:
式 (2.7.20-a):
References
| ↑1 | [訳註] 式 (2.7.3) のように書き表した場合では |
|---|---|
| ↑2 | [訳註] 最初の式は, 相対論的な速度の合成則 |
| ↑3 | [訳注] 原書では反変ベクトルも共変ベクトルも区別なく共に下付きの添字で表現しており, 4元勾配は |
| ↑4 | [訳注] ランダウ:「力学・場の理論」を参照のこと.そこで用いられている計量テンソルは |
| ↑5 | [訳注] 4元ベクトル |
| ↑6 | [訳注] |
| ↑7 | これは |