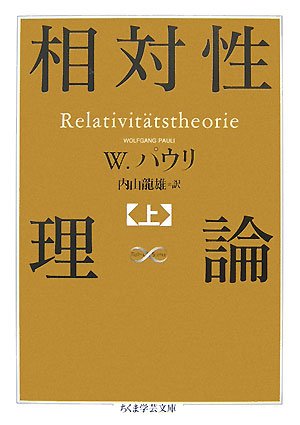前のブログ記事 [1] ローレンツ力による電荷の運動方程式 で「ローレンツ力による電荷の運動方程式はマックスウェル方程式には含まれないらしい」と書いた.W.パウリ:「相対性理論 (上)」(ちくま学芸文庫) の§ 29 に, このことを確認できる記述があったので, この本から関連する箇所を抜粋しておこう.
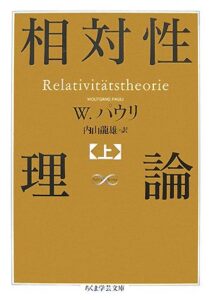
§ 28 電子論の基礎方程式の共変性
すでに§ 1 でも述べたように, ガリレイ変換に対してマックスウェルの方程式が不変でないことが相対性理論を誕生させる一つの大きな誘因となった.Lorentz は彼の1904 年の論文に於いて, 現在われわれが「ローレンツ変換」と呼んでいる変換に対してマックスウェルの方程式が不変であることを証明した.しかしこの証明は電荷や電流が存在しない場合に限られていた.電荷, 電流が存在する場合をも含めて, 方程式の不変性を完全に証明したのは Poincaré (およびこれと独立に Einstein)である.またマックスウェルの方程式を4次元テソソル形式に書きなおしたのは Minkowski である.彼は“面テソソル” [2][ブログ註] ベクトルは与えられた長さを持った一つの線分で表わすことが出来るので, … Continue reading の概念を重視した最初の人である.
さて電磁場の方程式を4 次元的に不変な形式で書き下すために, まず電荷密度,電流密度に関係しない4 個の方程式を取り上げよう:
いま虚時間座標を用いて,
とおけば, 式(B)は
あるいは,
のようにまとめられる [式 (140b) を参照] [3][ブログ註] ベクトル場
となる.そこで式 (142) と式 (141b) を使うと, 式 (203) は,
となる.しかし,普通の
この結果を見ると, 場の量を電場と磁場に分割することは ただ相対的な意味をもつだけであることが分かる.すなわち,
電磁場のスカラー・ポテンシャル及び Lorentz の理論に出て来るベクトル・ポテンシャル
である.電磁場の強さをポテンシャルを用いて表わす公式
は, 4次元的形式で書くと次となる:
4元ポテンシャルは元来, 数学的な補助的量ではあるが大変便利な量である.しかし Lorentz の電子論では, 直接的な物理的意味を持つものではない. 式 (206) からは, 場の方程式 (203) が導かれる.逆に式 (203) が成立すれば, ペクトル
という条件が付けられている.この条件を4次元的に書けば次となる:
Lorentz のポテンシャルには
電荷や電流密度を含むマックスウェルの方程式の第2組は,
である.これも式 (B) と同じように4次元的に書き換えられる [式 (145) を参照]:
もし電荷・電流密度を式 (208) [または式 (C)] で定義するとすれば, 式 (208) の左辺のベクトル性から
従って, 式 (208) は次のように書き表せる:
式 (207)の
いままで述べてきたように, 電磁場の方程式はローレンツ群に対してその形を変えない(共変性).そこでこの方程式の共変性を破らない, ローレンツ群よりも大きな変換群が存在しないだろうかと考えてみることは当然と言えよう.この質問に対する解答は Cunningham および Bateman により与えられた.彼等によれば, そのような群の中で最も一般的な群は, 光円錐の方程式
をそれ自身に変換するような「アフィン変換」の全体から構成される群である [§8の式 (B’) のことである].この群はローレンツ群を部分群に持つが, それを別にしたとき, 更にこの群は虚時間座標を用いた場合, 4次元球 (実時間を用いるならば4次元双曲面) による「鏡像変換」を含む.Weyl の「統一場理論」が発表されてからは, Bateman の定理には新たな光が差し込んだ [第 V 篇参照]. また P.Frank は次のことに対する簡単な証明をあたえた.すなわち「マックスウュルの方程式を共変にする線形変換群は, ローレンツ変換と普通の相似変換を一緒にした群以外には存在しない」ということである.
§ 29 電磁的力.電子の力学
Einstein は彼の第1論文ですでに次のことを示した.すなわち, もし電磁場内を無限に小さな速度を持って運動している点電荷の運動の法則が分かっているとき, 相対性理論を用いれば, 任意の大きさの速度を持って電磁場の中を運動する点電荷の行動について明確な予言をすることが可能であるということである.ここで言う点電荷とは, 電荷をもった物体の拡がりがその物体の内部では外部からこれに働く電磁場が一様であると見なせるほどに小さなものを意味する.従って点電荷というときは, それは必ずしも電子を指すとは限らない.いま座標系
ここで式 (204) そして次の加速度の変換公式 (194) を用いる: [6][ブログ註] (§ 26 の「加速度の変換則」より) 速度の変換則は3次元速度
すると, 座標系
ただし
この結果をながめると, まずこの右辺はまさに「ローレンツ力」となっていることが分かる.もともとは, 口ーレンツ力については, マックスウェル方程式とは独立に一つの要請として, よく知られているその数学的形式が提唱された.しかし相対性理論では, 上の導き方からも分かるように式 (210) と相対性原理から必然的に出て来る.しかしここで次のことに注意しなければならない.すなわち, 上に述べたことは,
が相対論における力である.なぜならば, この式 (212) だけがまさに運動量の時間微分に等しくなることが分かるからである [相対性理論でも外力が作用していない閉じた物理系では, 運動量は時間的に一定でなければならない](§ 37 を参照).式 (204)と式 (212) から力に対する変換則が導かれる:
この式を導くのに, この電磁的力が作用している荷電体は, 問題にしている瞬間に座標系
古い文献では
と書きかえる方がもっと便利である.このようにすれば式 (215) で定義された
References
| ↑1 | ローレンツ力による電荷の運動方程式 |
|---|---|
| ↑2 | [ブログ註] ベクトルは与えられた長さを持った一つの線分で表わすことが出来るので, ベクトルのことを「線テンソル」と呼ぶ.線より1次元だけ高い次元の幾何学的実体は面である.面に対応して「面テンソル」が存在する.これは2階反対称テンソルである.これは2個のベクトル |
| ↑3 | [ブログ註] ベクトル場 ベクトル場 これはスカラー場の一つであり, 3次元空間の発散 |
| ↑4 | [ブログ註] 「軸性ベクトル」は2つの極性ベクトルのベクトル積として表せる.2つの「極性ベクトル」あるいは2つの「軸性ベクトル」のスカラー積は, 「真のスカラー」である.すなわち, それは反転に対して不変である.軸性ベクトルと極性ベクトルとのスカラー積は「擬スカラー」である.それは反転に際して符号を変える.例えば, 電場と磁場はポテンシャルにより次の様に表せる: 従って, |
| ↑5 | [ブログ註] (C.メラー:相対性理論より) 慣性系 を不変にする斉1次変換で与えられる.次に と置けば, 斉次Lorentz変換は斉1次変換 で表わすことが出来る.ただし, その際に という条件が満たされていなければならない.特に となるから,この時の係数 座標系 電場 このとき独立な成分は次の6個である: この 従って, 回転を伴わない一般のLorentz変換に対しては, これを速度 電磁場は, その測定に用いられる器具の制約によって, 電場と磁場に分けられているが, この様に分けることは何ら絶対的な意味を持っていない.例えば, |
| ↑6 | [ブログ註] (§ 26 の「加速度の変換則」より) 速度の変換則は3次元速度 ただし 4元加速度 この を用いて次のように求まる: 特に, いまある瞬間に また, この両辺に上の式を代入すると, これは既に Einstein の第1論文に出て来たものである. |