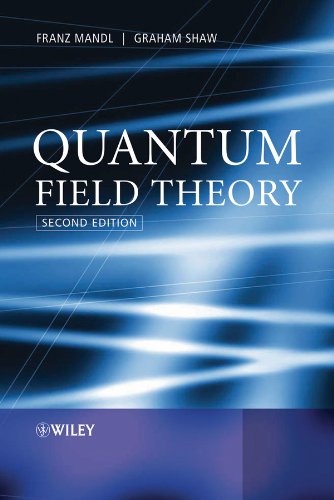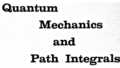\(\)
問題 8-7 は,「場の理論」に関係している.そこで, F. Mandel著:「Quantum Field Theory」から第2章の「ラグランジュ形式の場の理論」などから関係する部分を抜粋し要約したものを示しておく.
2 ラグランジ形式の場の理論
2.1 相対論的表記法
時間成分が \(x^{0}=ct\) で, 空間座標が \(x^{j}\,(j=1,2,3)\) である時空4-ベクトルを \(x^{\mu}\) と書くことにする.すなわち \(x^{\mu}=(ct,\mathbf{x})\) .4-ベクトルの成分はギリシャ文字の添字で表示し, 空間の3-ベクトルの成分はローマ字の添字で表示する.
次の成分を持つ計量テンソル \(g_{\mu\nu}\) を用いて, 共変ベクトル \(x_{\mu}\) は反変ベクトル \(x^{\mu}\) から定義する:
\def\ppdiff#1#2{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\def\pdiff#1{\frac{\partial}{\partial #1}}
\def\reverse#1{\frac{1}{#1}}
\def\Bpdiff#1{\frac{\partial^{2}}{\partial #1^{2}}}
\def\Bppdiff#1#2{\frac{\partial^{2} #1}{\partial #2^{2}}}
\def\mb#1{\mathbf{#1}}
g_{\mu\nu}\begin{cases} g_{00}=-g_{11}=-g_{22}=-g_{33}=+1, \\ g_{\mu\nu}=0\quad \mathrm{if}\ \mu\ne \nu \end{cases}
\quad \rightarrow \quad x_{\mu}=\sum_{\nu=0}^{3}g_{\mu\nu}x^{\nu}\equiv g_{\mu\nu}x^{\nu}
\tag{2.1, 2.2}
\end{equation}
最後の式では和の規約を用いた:「ギリシャ文字の添字が反変的なものと共変的なものとして繰り返されるときは和をとる」.式 (2.1) と式 (2.2) から, 共変ベクトルは \(x_{\mu}=(ct,-\mb{x})\) である.
反変的な計量テンソル \(g^{\lambda\mu}\) も, 次式によって定義する:
g^{\lambda\nu}g_{\mu\nu}=g^{\lambda}_{\nu}=\delta^{\lambda}_{\nu}
\tag{2.3}
\end{equation}
ただし \(\delta^{\lambda}_{\nu}\) は通常のクロネッカーデルタである: \(\delta^{\lambda}_{\nu}=1\) if \(\lambda=\nu\) and \(\delta^{\lambda}_{\nu}=0\) if \(\lambda\ne \nu\).式 (2.1) と式 (2.3) より, \(g^{\mu\nu}=g_{\mu\nu}\) である.
次のローレンツ変換は \(x^{\mu}x_{\mu}\) を不変に保つ:
x^{\mu}\rightarrow x’^{\mu}=\Lambda^{\mu}_{\nu}x^{\nu},\quad x^{\mu}x_{\mu}=\bigl(x^{0}\bigr)^{2}-\mb{x}^{2}
\tag{2.4, 2.5}
\end{equation}
従って \(x’^{\mu}x’_{\mu}=x^{\mu}x_{\mu}\) はスカラー量である.よって次が言える:
\Lambda^{\lambda\nu}\Lambda_{\lambda\nu}=\delta^{\mu}_{\nu}
\tag{2.6}
\end{equation}
(更に, 行列 \(\Lambda^{\lambda\mu}\) は, それが時空座標であることを保証するためには実数でなければならない).
ローレンツ変換の元では, 4-成分対象 \(s^{\mu}\,(s_{\mu})\) は \(x^{\mu}\,(x_{\mu})\) と同じ変換をし, 従って \(s^{\mu}s_{\mu}\) が不変となるので, それは反変な (共変な) 4-ベクトルである.その例は, エネルギー-運動量ベクトル \(p^{\mu}=(E/c,\mb{p})\) である.混乱が生じないときには, テンソルの添字はしばしば省略することにする.例えば, \(x^{\mu}\) や \(x_{\mu}\) は \(x\)と書いて良かろう.
4-ベクトル \(a\) と \(b\) のスカラー積は, 様々な仕方で書くことが出来る:
ab = a^{\mu}b_{\mu}=a_{\mu}b^{\mu}=g_{\mu\nu}a^{\mu}b^{\nu}=\dotsb =a^{0}b^{0}-\mb{a}\cdot\mb{b}
\tag{2.7}
\end{equation}
従って \(x^{2}=x^{\mu}x_{\mu}\) と同様に, スカラー積 \(ab\) はローレンツ変換の下で不変である.
勾配ベクトル \(\nabla\) を 4-次元へ一般化したものは, 4-ベクトルと同じ変換をする.もし \(\phi(x)\) がスカラー関数である, すなわち
\delta \phi =\ppdiff{\phi}{x^{\mu}}\delta x^{\mu},
\end{equation*}
であるならば,
\[\ppdiff{\phi}{x^{\mu}}\equiv \partial_{\mu}\phi \equiv \phi_{,\,\mu}\tag{2.8a}\]
は, 共変的な4-ベクトルである.同様に,
\[\ppdiff{\phi}{x_{\mu}}\equiv \partial^{\mu}\phi \equiv \phi_{,}^{\ \mu}\tag{2.8b}\]
は, 反変的な4-ベクトルである.コンマに続く添字は微分を表わすこと注意する.最後に,「ダランベール演算子」:\(\square\) はスカラーである ことにも注意する:
\partial^{\mu}\partial_{\mu} = \frac{1}{c^{2}}\Bpdiff{t}-\nabla^{2}\equiv \square
\tag{2.9}
\end{equation}
2.2 ラグランジュ形式の古典的な場の理論
特定するのに数個の場 \(\phi_r(x),\ r=1,2,\dotsb,N\) を必要とするような系を考えることにしよう. 添字 \(r\) は, 同じ場の成分たち [例えば, ベクトルポテンシャル \(\mb{A}(x)\) の成分たち]を表わしてもよいし, または,独立した異なる場たちを言及するのでもよい.ここで扱う理論は, 次のようなラグランジアン密度を含んだ作用積分から変分原理によって導出されるような理論に限定する:
\[L=\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{L},\quad \mathscr{L}=\mathscr{L}(\phi_r,\phi_{r,\alpha})\tag{2.10}\]
ただし導関数 \(\phi_{r,\alpha}\) は式 (2.8a) で定義された \(\phi_{r,\alpha}=\partial_{\alpha}\phi_r\) とする.式 (2.10) の「ラグランジアン密度」\(\mathscr{L}\) は, 場とその1次微分だけに依存するが,それは可能な最も一般的な場合ではない.この本で議論される全ての理論をカバーし, そして形式を非常に簡単化するものである.
4次元の時空連続体の任意な領域 \(\Omega\) に対する「作用積分」\(S(\Omega)\) を次で定義する:
\[S(\Omega)=\int dt L=\int dt\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{L}=\int_{\Omega}d^{4}x\,\mathscr{L}(\phi_r,\phi_{r,\alpha})\tag{2.11}\]
ただし \(d^{4}x\) は4次元要素 \(dx^{0}d^{3}\mb{x}\) を表わしているとする.
さて次に, 運動方程式すなわち場の方程式は, 力学のハミルトンの原理に非常に類似した「変分原理」から得られると仮定する.任意の領域 \(\Omega\) に対して, 次のような場の変分を考える:
\phi_r(x)\rightarrow \phi_r(x)+\delta\phi_r(x)
\tag{2.12}
\end{equation}
ただし, それは領域 \(\Omega\) の境界となる表面 \(\Gamma(\Omega)\) 上でゼロになるものとする:
\delta \phi_r(x)=0\quad \mathrm{on}\quad \Gamma(\Omega)
\tag{2.13}
\end{equation}
場 \(\phi_r\) は実数でも複素数でもよい.複素数の場 \(\phi(x)\) である場合, 場 \(\phi(x)\) と \(\phi^{*}(x)\) は2つの独立な場として扱われる.その代わりに, 複素数の場 \(\phi(x)\) を一対の実数場に分解することも出来る.すると, 任意の領域 \(\Omega\) そして変分 (2.12)\(\sim\) (2.11) に対して, 作用 (2.11) は「停留値」を持つ.すなわち,
\[\delta S(\Omega)=0\tag{2.14}\]
式 (2.11) から \(\delta S(\Omega)\) を計算すると, 部分積分をすることで次を得る [1]式 (2.15) とそれ以降では, 「添字 \(r\)や\(\alpha\) が繰り返されて積となる場合には和をとること」が暗黙の了解となる. :
\delta S(\Omega)&=\int_{\Omega} d^{4}x\,\left\{\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_r}\delta\phi_r
+\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\delta\phi_{r,\alpha}\right\}\notag\\
&=\int_{\Omega} d^{4}x\,\left\{\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_r}-\pdiff{x^{\alpha}}
\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\right)\right\} \delta\phi_{r}
+\left[\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\delta\phi_r\right]_{\Gamma(\Omega)}
\tag{2.15}
\end{align}
なぜなら, 部分積分から次が成り立つからである:
\begin{align*}
&\delta\phi_{r,\alpha}=\delta\left(\ppdiff{\phi_r}{x^{\alpha}}\right)=\pdiff{x^{\alpha}}\delta \phi_r,\\
\rightarrow&\quad \int_{\Omega} d^{4}x\,\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\pdiff{x^{\alpha}}\delta \phi_r
=\left[\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\delta\phi_r\right]_{\Gamma(\Omega)}
-\int_{\Omega} d^{4}x\,\pdiff{x^{\alpha}}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\right)\delta\phi_r
\end{align*}
このとき, 式 (2.13) から \(\delta\phi_r=0\) なので, 最初の表面積分項はゼロとなる.もし任意領域 \(\Omega\) と任意の変分 \(\delta\phi_r\) に対して \(\delta S(\Omega)\) がゼロとなるならば, 式(2.15) は「オイラーラグランジュの方程式」となる:
\[\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_r}-\pdiff{x^{\alpha}}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\right)=0,\qquad r=1,\dotsb,N\tag{2.16}\]
これらは,「場の運動方程式」である.
【 補足 】 参考として, J.J.Sakurai著「Advanced Quantum Mechanics」の §1-2, 1-3 からの抜粋を多少修正して示しておく.
1個の粒子, より正確には古典力学に於ける質点, の力学的な振舞いは, 次のラグランジュの運動方程式から推論する(infer) ことが出来る:
\frac{d}{dt}\left(\ppdiff{L}{\dot{q}_i}\right)-\ppdiff{L}{q_i}=0
\tag{1.1}
\end{equation}
この方程式は「ハミルトンの変分原理」から導出可能(derivable) である:
\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_i,\dot{q}_i)\,dt = 0
\tag{1.2}
\end{equation}
ここで, 一般化座標 \(q_i\) の離散的な力学系から, 一般化座標 \(\eta\) の連続的な力学系に移行する:
\delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt
=\delta\int_{t_1}^{t_2} dt\int_{x_1}^{x_2} dx\,\mathscr{L}\left(\eta,\dot{\eta},\ppdiff{\eta}{x}\right) = 0
\tag{1.10}
\end{equation}
このとき \(\eta\) は連続変数 \(x\) 及び \(t\) の関数 \(\eta=\eta(x,t)\) となる.\(\eta\) の変分 \(\delta\eta\) は \(t_1\) 及び \(t_2\) に於いてゼロであると仮定されるが, 空間積分の端点(extremity) \(x_1,x_2\) に於いてもゼロであると仮定される.(場の理論では, この後者を明示的には言及しない.なぜなら, 通常では無限遠で十分急激にゼロとなる場を考えるからである).そうでないならば, 変分の性質は完全に任意である.すると作用積分 \(S\) の変分は,
\begin{align*}
\delta S &=\delta \int L\,dt=\delta\int dt \int \mathscr{L}\,dx =\int dt\int dx\,\delta\mathscr{L}\\
&= \int dt\int dx\,\left\{ \ppdiff{\mathscr{L}}{\eta}\delta\eta
+\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\delta\left(\ppdiff{\eta}{x}\right)
+\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\delta\left(\ppdiff{\eta}{t}\right)\right\},
\end{align*}
ここで,
\[ \delta\left(\ppdiff{\eta}{x}\right)=\pdiff{x}\delta\eta,\quad \delta\left(\ppdiff{\eta}{t}\right)=\pdiff{t}\delta\eta \]
であることに注意し, さらに部分積分することで次が言える:
\begin{align*}
\int dx\,\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\pdiff{x}\delta\eta
&=\left[\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\delta\eta \right]_{x_1}^{x_2}
-\int dx\,\pdiff{x}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\right)\delta\eta\\
&=-\int dx\,\pdiff{x}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\right)\delta\eta,\\
\int dt\,\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\pdiff{t}\delta\eta
&=\left[\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\delta\eta \right]_{t_1}^{t_2}
-\int dt \,\pdiff{t}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\right)\delta\eta\\
&=-\int dt \,\pdiff{t}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\right)\delta\eta
\end{align*}
このとき 各々の第1項は, 上述の仮定からゼロとなる.従って \(\delta S\)は,
\delta S &=\delta\int L\,dt\notag\\
&=\int dt\int dx\,\left\{ \ppdiff{\mathscr{L}}{\eta}\delta\eta
-\pdiff{x}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\right)\delta\eta
-\pdiff{t}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\right)\delta\eta\right\}\notag\\
&=\int dt\int dx\,\left\{ \ppdiff{\mathscr{L}}{\eta}
-\pdiff{x}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\right)
-\pdiff{t}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\right)\right\}\delta\eta
\tag{1.11}
\end{align}
上述の要件を満たすどんな任意の変分に対しても, 式 (1.11) がゼロとなるべきとするならば, 被積分項の \(\{\,\}\) 内はゼロでなければならない.従って,
\pdiff{x}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial x)}\right)
+\pdiff{t}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\eta/\partial t)}\right)-\ppdiff{\mathscr{L}}{\eta}=0
\tag{1.12}
\end{equation}
これは「Euler-Lagrange方程式」と呼ばれている.また,ハミルトニアン密度 \(\mathscr{H}\) は次のように定義することが出来る:
\mathscr{H}=\dot{\eta}\ppdiff{\mathscr{L}}{\dot{\eta}}-\mathscr{L}
=\dot{\eta}\,\pi-\mathscr{L},\quad \pi\equiv \ppdiff{\mathscr{L}}{\dot{\eta}}
\tag{1.14}
\end{equation}
このときの \(\partial\mathscr{L}/\partial\dot{\eta}\) は「\(\eta\) に共役な正準運動量」と呼ばれ, しばしば \(\pi\) と表記される.
以上の結果は容易に3次元系へ一般化できる.各時空点 \((\mb{x},t)\) に於いて定義される実数関数 \(\phi_r\) を考える. \(\mathscr{L}\) は, 今度は \(\phi_r\), \(\partial\phi_r/\partial x_k\,(k=1,2,3)\) そして \(\partial\phi_r/\partial t\) に依存する.4元-ベクトル記法を導入するならば, Euler-Lagrange 方程式は, マンデルの式 (2.16) に一致した形となる:
\[\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_r}-\pdiff{t}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\phi_r/\partial t)}\right)-\sum_{k=1}^{3}\pdiff{x_k}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\phi_r/\partial x_k)}\right)=0,\tag{1.12′}\]
\[\rightarrow\quad \ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_r}-\pdiff{x^{\alpha}}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{r,\alpha}}\right)=0\tag{2.16}\]
この古典理論を非相対論的量子力学の正準形式で量子化するためには, 共役変数を導入する必要がある. いま扱っているのは連続無限個の自由度を持つ系であり, それは, 空間 \(\mb{x}\) の各点に於いて時間の関数として考えられる場 \(\phi_r\) の値に相当している.我々はこの系を再び可算自由度を持つ系で近似し, 最終的に連続体極限まで行くことにする.
ある時刻 \(t\) の瞬間に於ける系を考える.そして3次元空間, すなわち平坦な空間的表面 \(t=\)const. を, 添字 \(i\) でラベル付けされた等体積 \(\delta\mb{x}_i\) の小さな小室に分解してみる.各小室内の「場の値」は, 例えば小室の中心 \(\mb{x}=\mb{x}_i\) での値で近似する.すると系は, 次の離散的な一般化座標集合によって記述される:
q_{ri}(t)\equiv \phi_r(i,t)\equiv \phi_r(\mb{x}_i,t),\quad r=1,\dotsb,N,\quad i=1,2,\dotsb
\tag{2.17}
\end{equation}
これは, 離散的格子点 \(\mb{x}_i\) に於ける「場の値」である.また, 場の空間微分を隣接する位置間の差分係数に置き換えると, 離散系のラグランジアンは次のように書くことが出来る:
L(t)=\sum_i \delta\mb{x}_i\,\mathscr{L}_i\bigl(\phi_r(i,t),\dot{\phi}_r(i,t),\phi_r(i’,t)\bigr)
\tag{2.18}
\end{equation}
ただし, ドットは時間微分を意味している.空間微分を差分で近似したために, \(i\) 番目の小室に於けるラグランジアン密度 \(\mathscr{L}_i\) は, 隣接する格子位置 \(i’\) での場に依存する.\(q_{ri}\) に共役な運動量は, 次のような通常のやり方で定義する:
p_{ri}(t)=\ppdiff{L}{\dot{q}_{ri}}\equiv \ppdiff{L}{\dot{\phi}_{r}(i,t)}\equiv \pi_r(i,t)\,\delta\mb{x}_i
\tag{2.19}
\end{equation}
ただし,
\pi_r(i,t)\equiv \ppdiff{\mathscr{L}_i}{\dot{\phi}_r(i,t)}
\tag{2.20}
\end{equation}
すると, 離散的な系のハミルトニアンは次で与えられる:
H=\sum_i p_{ri}\dot{q}_{ri}-L =\sum_i \delta\mb{x}_i\Big\{\pi_{ri}(i,t)\dot{\phi}_{r}(i,t)-\mathscr{L}_i\Big\}
\tag{2.21}
\end{equation}
極限 \(\delta\mb{x}_i\to 0\) を取ること, つまり小室サイズと格子間隔をゼロに縮めること, を期待して(with a view), \(\phi_r(x)\) に共役な場 \(\pi_r(x)\) を次で定義する:
\pi_r(x)=\ppdiff{\mathscr{L}}{\dot{\phi}_r}
\tag{2.22}
\end{equation}
\(\delta\mb{x}_i\to0\) の極限をとるとき, \(\pi_r(i,t)\) は \(\pi_r(\mb{x}_i,t)\) に向かって行き, そして離散的なラグランジアンとハミルトニアン関数 (2.18) と式 (2.21) は次となる:
L(t)=\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{L}(\phi_r,\phi_{r,\alpha}),\quad
H=\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{H}(x),
\tag{2.23, 2.24}
\end{equation}
ただし, ハミルトニアン密度 \(\mathscr{H}(x)\) は次で定義される:
\mathscr{H}(x)=\pi_r(x)\dot{\phi}_r(x)-\mathscr{L}(\phi_r,\dot{\phi}_{r,\alpha})
\tag{2.25}
\end{equation}
そして式 (2.23) と式 (2.24) 中の積分は, 時刻 \(t\) に於ける全空間に渡って行う.この場合のラグランジアン密度は, 時間には明示的に依存していないので, ハミルトニアン \(H\) が時間的に一定であるのは勿論のことである.
例として, \(\mu\) を次元 \(\mathrm{length}^{-1}\) を持つ定数とした時の, 一つの実数の場 \(\phi(x)\) に対する次のラグランジアン密度を考えよう:
\mathscr{L}&=\frac{1}{2}\Bigl(\phi_{,\alpha}\phi_{,}^{\,\alpha} – \mu^{2}\phi^{2}\Bigr)
=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{c}\ppdiff{\phi}{t}\right)^{2}-\bigl(\nabla\phi\bigr)^{2}-\mu^{2}\phi^{2}\right]\notag\\
&=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{c^{2}}\dot{\phi}^{2}-\bigl(\nabla\phi\bigr)^{2}-\mu^{2}\phi^{2}\right]
\tag{2.26}
\end{align}
次の章で, この場の量子は「換算コンプトン波長が \(\mu^{-1}\) 即ち \(\hbar\mu/c\)の 粒子質量で [2]コンプトン波長は\(\lambda_c/2\pi=\hbar/mc\) であるから,
\begin{equation*}
\lambda_c/2\pi = \frac{\hbar}{mc}=\frac{1}{\mu},\quad\rightarrow\quad m=\frac{\hbar\mu}{c}
\end{equation*}
, スピンを持たない中性ボソン」であることが分かるであろう.この場に対する式 (2.16) の運動方程式を求めてみよう.まず,
\begin{align*}
&\mathscr{L}=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{c}\ppdiff{\phi}{t}\right)^{2}-\bigl(\nabla\phi\bigr)^{2}-\mu^{2}\phi^{2}\right],
\quad \ppdiff{\mathscr{L}}{\phi}=-\frac{1}{2}\mu^{2}\cdot2\phi=-\mu^{2}\phi\\
&\pdiff{x^{\alpha}}\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{,\alpha}}
=\pdiff{ct}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\partial\phi/\partial ct)}\right)
+\nabla\cdot\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{(\nabla\phi)}\right)
=\pdiff{ct}\left(\ppdiff{\phi}{ct}\right)+\nabla\cdot\left(-\nabla\phi\right)
\end{align*}
従って Euler-Lagrange 方程式 (2.16) は,
\begin{align*}
\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi}-\pdiff{x^{\alpha}}\left(\ppdiff{\mathscr{L}}{\phi_{,\alpha}}\right)
&=-\mu^{2}\phi-\left(\frac{\partial^{2}\phi}{c^{2}\partial t^{2}}-\nabla\cdot\nabla\phi\right)=0
\end{align*}
すなわち, 次の「クライン=ゴルドン方程式」となる:
\[\left(\frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}}\nabla^{2}\right)\phi+\mu^{2}\phi=0,\quad\rightarrow\quad\Bigl(\square +\mu^{2}\Bigr)\phi(x)=0\tag{2.27}\]
またこのとき, 式 (2.22) の共役な場は,
\pi(x)=\ppdiff{\mathscr{L}}{\dot{\phi}}=\frac{1}{2c^{2}}\cdot2\dot{\phi}=\frac{1}{c^{2}}\dot{\phi}(x)
\tag{2.28}
\end{equation}
であり, そして式 (2.25) のハミルトニアン密度は次となる:
\mathscr{H}(x)=\frac{1}{c^{2}}\dot{\phi}(x)\cdot\dot{\phi}(x)-\mathscr{L}
=\frac{1}{2}\Bigl[c^{2}\pi^{2}(x)+\bigl(\nabla\phi\bigr)^{2}+\mu^{2}\phi^{2}\Bigr]
\tag{2.29}
\end{equation}
3.1 実数のKlein-Gordon 場
静止質量 \(m\) の粒子の場合, エネルギーと運動量に次のような関係がある:
E^{2}=m^{2}c^{4}+c^{2}\mb{p}^{2}\quad\rightarrow\quad
\Bigl(E^{2}-c^{2}\mb{p}^{2}\Bigr)\phi(x)=m^{2}c^{4}\phi(x)
\tag{3.1}
\end{equation}
もし粒子を1個のスカラー関数 \(\phi(x)\) で記述することが出来るならば, 非相対論的な量子力学の処方
\mb{p}\to -i\hbar\nabla,\quad E\to i\hbar \pdiff{t}
\tag{3.2}
\end{equation}
を式 (3.1) に代入すると,
\begin{align*}
\Bigl(E^{2}-c^{2}\mb{p}^{2}\Bigr)\phi(x)
&=\left(i\hbar\pdiff{t}\right)^{2}-c^{2}\Bigl(-i\hbar\nabla\Bigr)
=-\hbar^{2}\Bpdiff{t}+c^{2}\hbar^{2}\nabla^{2}\\
&=-c^{2}\hbar^{2}\left(\frac{1}{c^{2}}\Bpdiff{t}-\nabla^{2}\right)\phi(x)=m^{2}c^{4}\phi(x)\\
\rightarrow\quad&\left(\frac{1}{c^{2}}\Bpdiff{t}-\nabla^{2}\right)\phi(x)=-\left(\frac{mc}{\hbar}\right)^{2}\phi(x)
\end{align*}
従って,
\[\left(\frac{1}{c^{2}}\Bpdiff{t}-\nabla^{2}\right)\phi(x)\equiv\square\phi(x)=-\left(\frac{mc}{\hbar}\right)^{2}\phi(x)\equiv -\mu^{2}\phi(x)\]
\[\therefore\quad \Bigl(\square + \mu^{2}\Bigr)\phi(x)=0,\quad \mu\equiv \frac{mc}{\hbar}\tag{3.3}\]
この式 (3.3) は「Klein-Gordon 方程式」と呼ばれる.「式 (3.3) は1個の粒子の方程式である」と解釈すると困難が生じる.それらの困難は, 正定値の粒子密度の定義および式 (3.1) から得られるエネルギー \(E\) に2つの符号が存在することに関連している.これらの困難さについては, 相対論的な1粒子方程式に典型的なものであることを述べるに止めよう.Klein-Gordon 場 \(\phi(x)\) のような場が量子化されたときに生じるこのような困難は「多粒子理論では発生しない」[3]式(3.2)を代入することで導出される1粒子の波動方程式と対比して, これはしばしば「第2量子化」と呼ばれる. ことが分かるであろう.Klein-Gordon 方程式は, スピン \(0\) を持った \(\pi\)-中間子(パイオン) や \(K\)-中間子を適切に記述することが出来る.
さて次は, Klein-Gordon 方程式 (3.3) を満たす実数のスカラー場 \(\phi(x)\) を考えていく.そのような場は, 電気的に中性な粒子に相当する.他方, 電荷を持った粒子は, 複素量の場によって記述される.
Klein-Gordon 方程式 (3.3) は, 次の「ラグランジアン密度」から導出することが出来る:
\mathscr{L}=\frac{1}{2}\Bigl(\phi_{,\alpha}\phi_{,}^{\ \alpha}-\mu^{2}\phi^{2}\Bigr)
=\frac{1}{2}\Bigl(\partial_{\alpha}\phi\,\partial^{\alpha}\phi -\mu^{2}\phi^{2}\Bigr)
\tag{3.4}
\end{equation}
そして, \(\phi\) に共役な場は次である:
\pi(x)=\ppdiff{\mathscr{L}}{\dot{\phi}}=\frac{1}{c^{2}}\dot{\phi}(x)
\tag{3.5}
\end{equation}
量子化すると, 実数の場 \(\phi\) はエルミート演算子となる:\(\hat{\phi}^{\dagger}=\hat{\phi}\).それは, 同一時間での交換関係を満足する:
\bigl[\hat{\phi}(\mb{x},t),\dot{\hat{\phi}}(\mb{x}’,t)\bigr]=i\hbar c^{2}\,\delta(\mb{x}-\mb{x}’),\quad
\bigl[\hat{\phi}(\mb{x},t),\hat{\phi}(\mb{x}’,t)\bigr]=\bigl[\dot{\hat{\phi}}(\mb{x},t),\dot{\hat{\phi}}(\mb{x}’,t)\bigr]=0
\tag{3.6}
\end{equation}
粒子との結び付きを確立するために, \(\phi(x)\) を Klein-Goldon 方程式解の完全集合で展開する:
\phi(x)&=\phi^{+}(x)+\phi^{-}(x),\tag{3.7a}\\
\mathrm{where}\quad &\phi^{+}(x)=\sum_{\mb{k}}\left(\frac{\hbar c^{2}}{2V\omega_{\mb{k}}}\right)^{1/2}
a(\mb{k})\,e^{-ikx},\tag{3.7b}\\
\mathrm{and}\quad &\phi^{-}(x)=\sum_{\mb{k}}\left(\frac{\hbar c^{2}}{2V\omega_{\mb{k}}}\right)^{1/2}
a^{\dagger}(\mb{k})\,e^{ikx}\tag{3.7c}
\end{align}
和は, 周期的境界条件で許される波数ベクトル \(\mb{k}\) について取る.ただし, この場合の \(k^{0}\) と \(\omega_{\mb{k}}\) は次で与えられる:
k^{0}=\frac{\omega_{\mb{k}}}{c}=+\sqrt{\mu^{2}+\mb{k}^{2}},\quad
p^{\mu}=\left(\frac{E}{c},\mb{p}\right)=\left(\frac{\hbar\omega_{\mb{k}}}{c},\hbar\mb{k}\right)
=\hbar\left(\frac{\omega_{\mb{k}}}{c},\mb{k}\right)=\hbar k^{\mu}
\tag{3.8a}
\end{equation}
すなわち \(k\) は粒子の「4-波数ベクトル」であり, その粒子の「質量は\(m=\mu\hbar/c\)」, 「運動量は\(\mb{p}=\hbar\mb{k}\)」, そして「エネルギー\(E=\hbar\omega\)」は次である:
E=\hbar\omega_{\mb{k}}=+\sqrt{m^{2}c^{4}+c^{2}(\hbar\mb{k})^{2}}
\tag{3.8b}
\end{equation}
「式 (3.7) 中で, 各々の演算子 \(a(\mb{k})\) が, そのアジョイント(随伴量) \(a^{\dagger}(\mb{k})\) と対になって出現する」という事実は「\(\phi\) がエルミートであること (\(\phi^{\dagger}=\phi\))」を保証している.
式 (3.7) と交換関係 (3.6) からは, 次の演算子 \(a(\mb{k})\) と \(a^{\dagger}(\mb{k})\) に対する交換関係を容易に得ることが出来る:
\bigl[a(\mb{k}),a^{\dagger}(\mb{k}’)\bigr]=\delta_{\mb{k}\,\mb{k}’},\quad
\bigl[a(\mb{k}),a(\mb{k}’)\bigr]=\bigl[a^{\dagger}(\mb{k}),a^{\dagger}(\mb{k}’)\bigr]=0
\tag{3.9}
\end{equation}
これらはまさに調和振動子の交換関係である.そして調和振動子についての全ての結果を引き継ぐことが出来る.特に演算子
N(\mb{k})=a^{\dagger}(\mb{k})a(\mb{k})
\tag{3.10}
\end{equation}
は, 固有値として占有数 \(n(\mb{k})=0,1,2,\dotsb)\) を持ち, それに対応して \(a(\mb{k})\)と\(a^{\dagger}(\mb{k})\)は, 運動量\(\hbar\mb{k}\) でエネルギー\(\hbar\omega_{\mb{k}}\) の粒子の消滅演算子と生成演算子である.
References
| ↑1 | 式 (2.15) とそれ以降では, 「添字 \(r\)や\(\alpha\) が繰り返されて積となる場合には和をとること」が暗黙の了解となる. |
|---|---|
| ↑2 | コンプトン波長は\(\lambda_c/2\pi=\hbar/mc\) であるから, \begin{equation*} \lambda_c/2\pi = \frac{\hbar}{mc}=\frac{1}{\mu},\quad\rightarrow\quad m=\frac{\hbar\mu}{c} \end{equation*} |
| ↑3 | 式(3.2)を代入することで導出される1粒子の波動方程式と対比して, これはしばしば「第2量子化」と呼ばれる. |