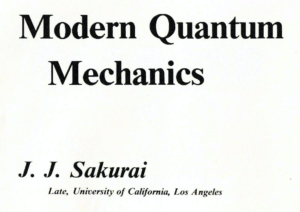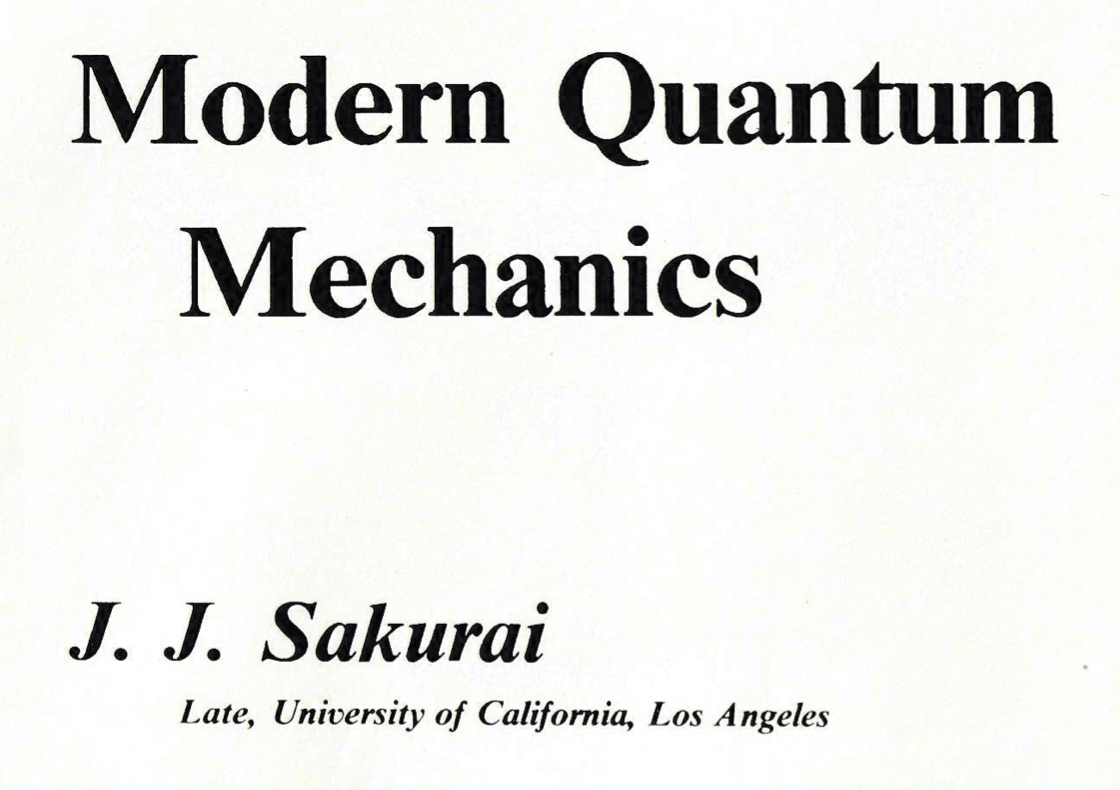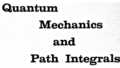前の記事に関連して, 以前「はてなブログ」に書いてあった2019年1月7日の記事を, わずかに修正しこちらに移して提示しておくことにする.
問題 6-23 では「運動量空間の波動関数」を用いて議論しているので, それについてJ.J.Sakurai の§ 1.7 から抜粋してまとめておこう.
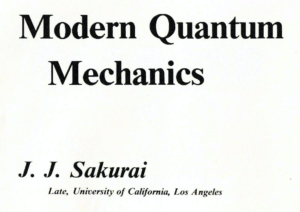
位置基底での運動量演算子
運動量演算子が – 基底ではどのように見えるかを調べる.出発点は「無限小平行移動演算子 」の「生成演算子」としての運動量 の定義である:
をケット に作用させると,
ただし最後の式変形では位置座標を だけズラした.この変形が出来る理由は, 積分区間は なので, 積分変数を に変更しても結果は変わらないからである.
さらに, 関数 の1次の近似式: を用いると, ケット 及びブラ は, 次のように近似して表せることに注意する:
すると, 式(2)は次のように変形される:
両辺の比較により次が言える:
また, 上式の両辺に左からブラ を掛け合わせると, 次の位置ケット の直交性:
を用いることで次が言える:
– 表示による の行列要素は, が位置ケット である場合を考えることで次のように求まる:
式(5)からは, 特に重要な恒等式が得られる:
この式が「仮定」ではなく, 「運動量の基本的性質を用いて導かれた」ことに注意する.
運動量空間の波動関数
運動量表示による1次元空間の波動関数を考える. – 基底に於ける固有ケットは次を満足する:
および,
運動量固有ケット は, ちょうど位置固有ケット と同じように, 連続スペクトルを示すケットベクトル空間を張る.従って, 任意の状態ケット は次のように展開できる:
この展開係数 に確率的解釈を付けることが出来る.つまり運動量 を測定して固有値 が狭い範囲 の間に得られる確率は次である:
を習慣上,「
運動量空間の波動関数」と呼び, しばしば という記号が用いられる:
式(12) を用いると, が規格化されているとき, 波動関数 も規格化されていることが示される:
– 表示から – 表示への変換は によってなされる.これは特に「
変換関数」と呼ばれる.
の具体的な表式を導くには式 (7) を利用することが出来る. を運動量の固有ケット にすると, 次が得られる:
に対するこの微分方程式の解は,
ただし はすぐ後で決められる「規格化定数」である.この変換関数 は, 運動量固有状態 を表わす波動関数と見做すことが出来る.つまり – 空間での運動量固有関数であり, 明らかに平面波である.この平面波の解が「シュレディンガー方程式を解かずに得られた」ことに注意する.
規格化定数 を求めるには, まず次式を考える:
この中の に具体的な形の式 (17) を代入し 関数の表現式の一つを用いると次が得られる:
上式から が求まるが, 慣行に習って を正の実数に選ぶと次となる:
以上の結果から, 式 (17) の「運動量固有関数」は次となる:
次に, 位置空間の波動関数が運動量空間の波動関数とどのように関係しているかを示しておく.そのためには次式を考えてみるだけでよい:
これら2式は 及び とすると, 次に書くことが出来る:
これらは互いに「
フーリエ変換」の関係になっていることに注意する.
( 参考) 上式 (24) に於いて が式 (21) の運動量固有関数 である場合を考えてみよう.すると,
従って,「平面波である運動量固有関数」に対応する「運動量空間の波動関数」は「 -関数」であることが分かった.運動量固有関数は運動量が確定した値 をもつ状態を表わすのであるから, これは当然の結果である.
最後に, 小出:「量子力学」の§ 3.5 波動関数と不確定性原理 に, 運動量固有関数の規格化についての言及があるので, その部分を抜粋して示しておこう:
平面波である運動量固有関数 を通常のように規格化することは出来ない.平面波すなわち運動量が一定となるような運動状態というのは, 力を受けていな粒子が行う等速度運動である.従って, 古典的に考えたときのその軌道は直線であり, 運動が一定の範囲の閉じた領域に限られるというものではない.量子論に移行しても同様で, 波動関数は何処か一定の点の近くだけに固まっているようなものではない.そもそも平面波では運動量の値が確定しているので, 不確定性原理から, 位置についての不確定度は無限大ということになる.つまり粒子が何処に居るかさっぱり分からないのである.このことは が位置 に依らず一定になるということに対応する.そうすると,
となるから, これを に等しいと置いて規格化すれば はゼロになってしまう.無限の空間のどこかに居る粒子など探しようがない訳である.この困難を避ける方法は色々考案されているが, ここでは一応規格化は諦めて, 相対確率だけを考えることにしよう.