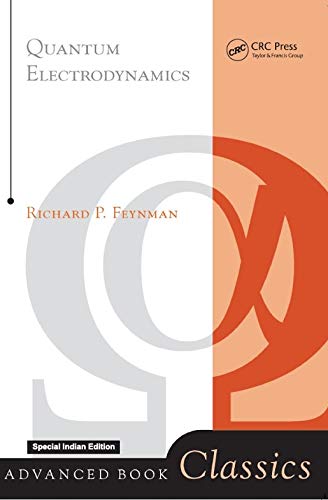自由空間に於けるマックスウェル方程式の解
自由空間(すなわち
の平面波解は [1][訳註] (ランダウ:「力学・場の力学」より) ポテンシャルの持つ任意性のため, … Continue reading,
ただし
これは
この演算に於いて
従って, 通常の表記では [2][訳註] 前講から4元座標は
そして, 条件
【 問題 】 ローレンツ条件:
(解答例) ローレンツ条件式
これが満たされるためには
3次元で作業する場合, 偏極ベクトル
ゲージ変換の式 (2.7.19) は次の2式に書ける:
ただし
従って, もし
が成り立つならば,
となるから,「ゲージ変換をしてもローレンツ条件の式 (2.7.20) は依然として成立する」であろう.方程式 (2.8.9) は, 解として
従って,
は, ゲージ変換によって得られる新たな偏極ベクトルである.通常の表記では, これは次の2式となる:
この両辺に
従って, どんな座標系を用いている場合でも, 定数
とすることが出来る.
場は明らかにゲージ変換を受けても変わらない.なぜなら, 微分の順序は重要ではないからである:
相対論的素粒子論(Relativistic Particle Mechanics)
「通常の(3次元)速度」の成分は 4-ベクトルの成分のようには変換しない.しかし, 別の量
は, 粒子の経路要素である (この
通常の速度
従って
「4元運動量」
従って, 通常の表記での「3次元運動量」
ここで
速度と同様に, 通常の力の成分は
この成分は次となる:
ただし
以上のことは,
ここで,
この関係を前式 (2.8.23) に代入すると,
従って, ニュートン方程式に類似した相対論的な式は次となる:[4][訳註] (C.メラー §27 より) 粒子の運動量が変化していれば, 粒子は単位時間当たりの運動量の変化に等しい力
通常のローレンツ力は,
そして, エネルギーの変化率(Power) は,
すると, 式 (2.8.22) の
となる.
【 問題 】
従って, ニュートンの運動方程式に相当する相対論的な式は次となる:
この式は, 次式が成り立つことを必要(前提)とする(imply):[5][訳註] 式(2.8.30)は, 原書では次となっている:
〈解答例〉 ある慣性系
これを踏まえて, この粒子が瞬間的に静止しているような慣性系
他方,
以上のことを踏まえて, 問題文の式 (2.8.29) の4元量を考える.静止系
よって
前節の結果式 (2.7.16) から,
であったから, これらを式 (5) に用いれば
すなわち, 静止系
以上の結果から, 式 (3) の4元力
以上は C.メラー:「相対性理論」 § 58 を参照した.
前述の式 (2.8.17) から
この式(10)から
である.この式 (11) と式 (8-1) から, 4元速度
通常の3次元的な力の表式は,
であった.これが式 (2.8.26) のローレンツ力である場合, 運動方程式は次となる:
ラグランジュ方程式
を直接適用して運動方程式 (8-4) を導くには, ラグランジアンを
とすればよいことを示すのは容易である.さらに,
これらに相当するハミルトニアンは
これは次式を満たす:
ハミルトニアンの考え方を「共変量」または「4次元の定式化」に変換するのは難しい.しかし,「作用
は運動方程式の相対論的な形を導出する.それは, 作用
このとき, 定義から次であることに注意する:
面白いことに, 次式で定義される別の「作用」
【 問題 】 (1) 式 (8-5) のラグランジアンは式 (8-4) の運動方程式を導出し, 相当するハミルトニアンは式 (8-6) であることを示せ.また,
(2)
〈解答例〉 (1) ランダウの §2 と §16 を要約することで答えに代える.
与えられた電磁場中で運動する粒子に対する作用は2つの部分から成る.すなわち, 自由粒子の作用
ここで
従って, 電磁場中の荷電粒子に対する作用関数の形は次のように成る:
粒子の速度は
「ラグランジュ方程式」は次である:
このとき,「一般化運動量」は,
ただし
ここで, よく知られた次のベクトル解析の公式を用いる:
ただし
となる.従ってラグランジュ方程式は次となる:
ところで, 微分
従って,
これを上式 (17.1-a) に用いると
従って, 次式が得られる:
さらに, 電場
これを上式 (17.2) に代入すれば,「電磁場中の電荷の運動方程式」として次が得られる:
このときの右辺の表現は「ローレンツ力」と呼ばれる.
一般公式
によって, ラグランジアンから「場中の粒子のハミルトニアン」を見出すことが出来る.式 (16.4) を代入すると, まず
従って,
ところが, ハミルトニアンは「一般化運動量」に表さなければならない.式 (16.5) と (16.6) から, 場が無い (
となるから,
これを書き直すと次となる:
(2) (ランダウの §2 から) 「最小作用の原理」は次の形に書ける:
あるいは「変分」を実行して,
従って, 次式を得る:
端点では変分はゼロであるという条件
このラグランジュ方程式を解くと 運動方程式 (8-4) を導くことが出来るのであるから, 結局式 (2.4) の
References
| ↑1 | [訳註] (ランダウ:「力学・場の力学」より) ポテンシャルの持つ任意性のため, 我々は常に付加条件をポテンシャルに課することが出来る.この理由のために, ここでは電磁波のポテンシャルをスカラー・ポテンシャルが方程式 |
|---|---|
| ↑2 | [訳註] 前講から4元座標は |
| ↑3 | [訳註] (ランダウ:「力学・場の理論」§35より) ある慣性基準系 |
| ↑4 | [訳註] (C.メラー §27 より) 粒子の運動量が変化していれば, 粒子は単位時間当たりの運動量の変化に等しい力 方程式 (24) は, 粒子の速度が小さいときには Newton の運動の第2法則に等しくなるが, この「方程式 (24) を相対論的領域に於ける力の定義を与える式」と見做すことにする.なぜなら, 粒子の運動量の変化を生じる原因である系の物理的状態に対する力 Newton 力学に於けると同様に, 単位時間当たりの力のする仕事 によって定義する.ここで によって定義される.この式は単位時間当たりの運動エネルギーの変化(Power)が, 仕事 従って, 4元運動量 |
| ↑5 | [訳註] 式(2.8.30)は, 原書では次となっている: しかし, この式の書き方では紛らわしいと思われたため修正して表記した. |
| ↑6 | [訳註] 原書では式 (2.8.34) 式 (8-5) のラグランジアンに於いて「速度が小さい場合」には 従って, ラグランジアンは次のように近似される: さらに「ラグランジアンの決定には, 座標と時間の任意関数の時間についての完全導関数 そこで上述の 従って, このラグランジアン |