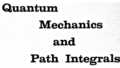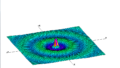\(\)
問題 6-25 の解答の準備として, ランダウ=リフシッツ物理学小教程:「力学・場の理論」の第14章 電磁波の放射 から必要な部分を抜粋し, その要点をまとめておこう.
遅延ポテンシャル
運動している電荷が作る場のポテンシャルを定める方程式を導いてみる. 電場と磁場は場のポテンシャルを用いて次で定義された:
\def\bra#1{\langle#1|}
\def\BK#1#2{\langle #1|#2\rangle}
\def\BraKet#1#2#3{\langle#1|#2|#3\rangle}
\def\ppdiff#1#2{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\def\odiff#1{\frac{d}{d #1}}
\def\pdiff#1{\frac{\partial}{\partial #1}}
\def\Bppdiff#1#2{\frac{\partial^{2}#1}{\partial #2^{2}}}
\def\Bpdiff#1{\frac{\partial^{2}}{\partial #1^{2}}}
\def\ds#1{\mbox{${\displaystyle\strut #1}$}}
\def\ket#1{|#1\rangle}
\def\mb#1{\mathbf{#1}}
\mb{E}=-\frac{1}{c}\ppdiff{\mb{A}}{t}-\mathrm{grad}\, \phi,\quad \mb{H}=\mathrm{rot}\,\mb{A}
\tag{1}
\end{equation}
マックスウェル方程式の第1の組および第2の組は次である:
\left\{\quad
\begin{aligned}
\mathrm{rot}\,\mb{E}&=-\frac{1}{c}\ppdiff{\mb{H}}{t},\qquad\quad \mathrm{div}\,\mb{H}=0,\\
\mathrm{rot}\,\mb{H}&= \frac{4\pi}{c}\,\mb{j}+\frac{1}{c}\ppdiff{\mb{E}}{t},\quad \mathrm{div}\,\mb{E}=4\pi\rho
\end{aligned}
\right.
\tag{2}
\end{equation}
式 (1) を式 (2) の第2の組の第一式に代入し, ベクトル解析の公式 \(\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\mb{A}=\nabla(\nabla\cdot\mb{A})-\nabla^{2}\mb{A}\) を用いると次が得られる:
\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\mb{A}=\nabla(\nabla\cdot\mb{A})-\nabla^{2}\,\mb{A}
=\frac{4\pi}{c}\mb{j}-\frac{1}{c^{2}}\Bppdiff{\mb{A}}{t}-\nabla\left(\frac{1}{c}\ppdiff{\phi}{t}\right)
\tag{3}
\end{equation}
ベクトルポテンシャルに課す付加条件として, 次の「ローレンツ条件」と呼ばれる式を選ぶ:
\nabla\cdot\mb{A}+\frac{1}{c}\ppdiff{\phi}{t}=0
\tag{4}
\end{equation}
すなわち,「ローレンツ・ゲージ」のポテンシャルを考える訳である. このとき, 式 (3) の両辺の最後の項は互いに打ち消し, 次が得られる:
\nabla^{2}\,\mb{A} -\frac{1}{c^{2}}\Bppdiff{\mb{A}}{t}=-\frac{4\pi}{c}\,\mb{j}
\tag{5}
\end{equation}
同様にして, 式 (1) を式 (2) の第二式に代入して次が得られる:
-\frac{1}{c}\pdiff{t}\,\mathrm{div}\,\mb{A}-\nabla^{2}\phi =4\pi\rho
\tag{6}
\end{equation}
または, やはり式 (4) のローレンツ条件式を用いるならば次が求まる:
\nabla^{2}\phi -\frac{1}{c^{2}}\Bppdiff{\phi}{t} =-4\pi\rho
\tag{7}
\end{equation}
以上の式 (5) と式 (7) とが, 求めていた「運動している電荷が作る場のポテンシャルを定める方程式」である.
任意の電荷分布 \(\rho\) に対する非同次線形方程式である式 (5) と方程式 (7) の一般解, すなわち, 位置 \(\mb{r}’\) 近傍にある電荷 \(\rho(\mb{r}’,t)dV’\)が 観測位置 \(\mb{r}\) に作る場は, \(\mb{R}=\mb{r}-\mb{r}’\) としたとき次のように求まる:
\phi(\mb{r},t)&=\int \frac{1}{R}\,\rho\left(\mb{r}’,t-\frac{R}{c}\right)\,dV’+\phi_{0}\equiv \int \frac{\rho_{\,t-R/c}}{R}\,dV+\phi_{0},\tag{8}\\
\mb{A}(\mb{r},t)&=\frac{1}{c}\int \frac{1}{R}\,\mb{j}\left(\mb{r}’, t-\frac{R}{c}\right)\,dV’+\mb{A}_{0}\equiv \frac{1}{c}\int \frac{\mb{j}_{\,t-R/c}}{R}\,dV+\mb{A}_{0} \tag{9}
\end{align}
ただし \(R=|\mb{R}|\) は体積要素 \(dV’\) から観測地点までの距離である. 上式で, \(\phi_{0}\) 及び \(\mb{A}_{0}\) を省いた場合のポテンシャルは「遅延ポテンシャル」と呼ばれる:
\phi(\mb{r},t)=\int \frac{1}{R}\,\big[ \rho(\mb{r}’,t’)\big]_{ret}\,dV’ \quad
\mb{A}(\mb{r},t)=\frac{1}{c}\int \frac{1}{R}\,\big[\mb{j}(\mb{r}’,t’)\big]_{ret}\,dV’
\end{equation}
ここで, カギ括弧 \([\ ]_{ret}\) は, 時間 \(t’\) が遅延した時刻 (retarded time): \(t’=t-R/c\) で評価されることを意味している (この表現は J.D.Jackson:「電磁気学」から採った).
電荷系から遠く離れた地点での場
運動している電荷系が作る場の, 系の大きさに比べて遠い距離を隔てた場所に於ける様子を考察する. 「座標原点 O を, 電荷系内部の任意点にとる. O から場の大きさを決定しようとする点 P までの位置ベクトルを \(\mb{R}_{0}\) で表し, この方向の単位ベクトルを \(\mb{n}\) としよう. 電荷 \(dq=\rho\,dV\) の動径ベクトルを \(\mb{r}\) とし, \(dq\) から点 P までの動径ベクトルを \(\mb{R}\) とする. すると明らかに \(\mb{R}=\mb{R}_{0}-\mb{r}\) である.
電荷系から遠い処では, \(R_{0}\gg r\) である. 従って, 近似的に次が言える:
$$R=\big|\mb{R}_{0}-\mb{r}\big|\approx R_{0}-\mb{n}\cdot\mb{r}$$
これを遅延ポテンシャルの式 (8) と式 (9) に代入する. 積分に際して \(R_{0}\) は一定であるから積分の外へ出すことが出来る. よって, 電荷系から遠く離れた処でのポテンシャルとして次の表式が得られる:
\phi=\frac{1}{R_{0}}\int \rho_{\ t-R_{0}/c+\mb{r}\cdot\mb{n}/c}\,dV,\quad
\mb{A}=\frac{1}{c R_{0}}\int \mb{j}_{\ t-R_{0}/c+\mb{r}\cdot\mb{n}/c}\,dV
\tag{10}
\end{equation}
電荷系から十分遠く離れた処では, 空間のあまり大きくない領域範囲で「場を平面波と見做す」ことが出来る. そのためには距離が, 系の大きさに比べて大きいだけでなく, その系が放射する電磁波の波長に比べても大きいことが必要である. このような空間領域は放射の「波動帯」と呼ばれる.
平面波に於いては, 電場と磁場とは次式によって互いに関係づけられている:
\mb{E}=\mb{H}\times\mb{n}
\tag{11}
\end{equation}
よって, 平面波の電場 \(\mb{E}\) と磁場 \(\mb{H}\) とは波の伝搬方向に垂直に向いており, 電磁波は「横波」であることが分かる. また平面波の電場と磁場とは互いに直交し等しい大きさを持つことが分かる.
波動帯に於ける場を完全に決定するには, ベクトル・ポテンシャルだけを計算すれば十分である. そして, \(x\)-軸の方向に進む平面波のベクトル・ポテンシャルは常に \(x\)-軸に垂直に, すなわち, 波の伝搬方向に垂直に選ぶことが出来る. \(\mb{A}\) を知れば, 次の公式から \(\mb{H}\) 及び \(\mb{E}\) が求められる:
\mb{H}=\frac{1}{c}\dot{\mb{A}}\times\mb{n},\qquad \mb{E}=\frac{1}{c}\big(\dot{\mb{A}}\times\mb{n}\big)\times\mb{n}
\tag{12}
\end{equation}
電磁波の放射は勿論エネルギーの放射を伴う. 平面波である電磁波による「エネルギーの流れ」すなわち「ポインティング・ベクトル \(\mb{S}\)」は, 波のエネルギー密度を \(W=(E^{2}+H^{2})/8\pi\) とすると次である:
\mb{S}\equiv \frac{c}{4\pi}\mb{E}\times\mb{H}=\frac{c}{4\pi}E^{2}\,\mb{n}=\frac{c}{4\pi}H^{2}\,\mb{n}=cW\,\mb{n}
\tag{13}
\end{equation}
立体角要素 \(d\Omega\) の中に入る「放射の強度 \(dI\)」 は, 原点に中心を持つ半径 \(R_{0}\) の球面の要素 \(dA=R^{2}_{0}\,d\Omega\) を単位時間に通過するエネルギー量と定義される. それは明らかにエネルギー流の密度 \(S\) に \(dA\) をかけたものである. よって「放射強度」は次のように表される:
dI=S\cdot dA=\left(\frac{c}{4\pi}H^{2}\right)\cdot\left(R^{2}_{0}\,d\Omega\right)=c\frac{H^{2}}{4\pi}R_{0}^{2}\,d\Omega
\tag{14}
\end{equation}
更に, 質量がゼロで光速で動く粒子の運動量 \(p\) は, そのエネルギーを \(E\) として \(p=E/c\) であった. よって, 平面波である電磁波の運動量密度 \(P^{\mathrm{(em)}}\) は次である:
P^{\mathrm{(em)}}=\frac{\mb{E}\times\mb{H}}{4\pi c} =\frac{\mb{S}}{c^{2}}=\frac{W}{c}\mb{n}
\tag{15}
\end{equation}
双極放射
電荷系の大きさが放射される波の波長に比べて小さいか, または電荷の速度が光速度に比べて小さい場合には, 波動帯に於けるベクトル・ポテンシャルの式 (10) は, 時間 \(\mb{r}\cdot\mb{n}/c\) を無視できて, 次のように書くことが出来る:
\mb{A}=\frac{1}{c R_{0}}\int \mb{j}_{\ t’}\,dV, \quad \mathrm{where}\quad t’=t-R_{0}/c
\tag{16}
\end{equation}
このとき時間 \(t’\) はもはや積分変数に依存していない. よって \(\mb{j}_{\ t’}=\rho\mb{v}\) として, 次のように書き直す:
\mb{A}=\frac{1}{c R_{0}}\int \rho\mb{v}\,dV = \frac{1}{c R_{0}}\left(\sum q\,\mb{v}\right)
\tag{17}
\end{equation}
ただし和は系の全ての電荷にわたる. また, 右辺の全ての量は時間 \(t’\) に於けるものであるが, 簡略のために指標 \(t’\) は省いてあるので注意する.
更に, このとき
\sum q\,\mb{v} =\frac{d}{dt}\sum q\,\mb{r} = \dot{\mb{d}}
\tag{18}
\end{equation}
ただし, \(\mb{d}\equiv \sum q\,\mb{r}\) は系の「双極モーメント」である. よって,
\mb{A}=\frac{1}{c R_{0}}\,\dot{\mb{d}}
\tag{19}
\end{equation}
すると式 (12) より, 磁場と電場は次に等しいことが分かる:
\mb{H}=\frac{1}{c^{2} R_{0}} \ddot{\mb{d}}\times\mb{n},\qquad
\mb{E}=\frac{1}{c^{2} R_{0}} \big(\ddot{\mb{d}}\times\mb{n}\big)\times\mb{n}
\tag{20}
\end{equation}
よって, 今考えている近似では, 放射が電荷系の双極モーメントの2階導関数に依って決まることに注意する. この種の放射は「双極放射」と呼ばれる.
また, \(\mb{d}=\sum q\,\mb{r}\) より, \(\ddot{\mb{d}}=\sum q\,\dot{\mb{v}}\) であるから, 「電荷は加速度運動するときにのみ放射することが出来る」と言える.
式 (20) を式 (14) に代入すると, 「双極放射の強度」が得られる:
dI=c\frac{R_{0}^{2}}{4\pi}\left(\frac{\ddot{\mb{d}}\times\mb{n}}{c^{2}R_{0}}\right)^{2}\,d\Omega
=\frac{1}{4\pi c^{3}}\big(\ddot{\mb{d}}\times\mb{n}\big)^{2}\,d\Omega=\frac{\ddot{\mb{d}}^{2}}{4\pi c^{3}}\sin^{2}\theta\,d\Omega
\tag{21}
\end{equation}
ただし \(\theta\) は \(\ddot{\mb{d}}\) と \(\mb{n}\) の間の角度である. この \(dI\) は「単位時間に電荷系が立体角要素 \(d\Omega\) 内へ放射したエネルギー量」でもある. \(d\Omega=2\pi\sin\theta\,d\theta\) とおき, \(\theta\) で \(0\) から \(\pi\) まで積分すると次の式が得られる:
I=\int_{0}^{2\pi}d\phi\int_{0}^{\pi}\frac{\ddot{\mb{d}}^{2}}{4\pi c^{3}}\sin^{2}\theta\,\sin\theta\,d\theta
=\frac{\ddot{\mb{d}}^{2}}{2c^{3}}\int_{0}^{\pi}\sin^{3}\theta\,d\theta=\frac{\ddot{\mb{d}}^{2}}{2c^{3}}\cdot\frac{4}{3}
=\frac{2}{3c^{3}}\,\ddot{\mb{d}}^{2}
\tag{22}
\end{equation}
外場中で運動している電荷が一個であれば, \(\mb{d}=q\,\mb{r}\) であり, \(\mb{\alpha}\) をその粒子の加速度とすると \(\ddot{\mb{d}}=q\,\mb{\alpha}\) である. 従って, 加速度 \(\alpha\) で運動している電荷 \(q\) の全放射量は次となる:
I=\frac{2}{3c^{3}}q^{2}\alpha^{2}
\tag{23}
\end{equation}
もし電荷 \(q\) が振動数 \(\omega_{0}\) で「周期運動」をするならば, 双極モーメントそして放射の場はフーリエ級数に展開される. 「周期的な場 \(f(t)\)」のフーリエ級数展開は, \(T\) を場の周期として, 基本振動数 \(\omega_{0}=2\pi/T\) の整数倍の振動数を含み, 次の形に書くことが出来る:
f=\sum_{-\infty}^{\infty} f_{n}\,e^{-i\omega_{0}nt},\quad\mathrm{where}\quad f_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)e^{i\omega_{0}n t}\,dt
\tag{24}
\end{equation}
このとき, 場の2乗平均 (波の平均強度)は, 単色成分の強度の和の形に表される:
\overline{f^{2}}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} \big|f_{n}\big|^{2}=2\sum_{n=1}^{\infty} \big|f_{n}\big|^{2}
\tag{25}
\end{equation}
それに対して \(T\to\infty\) であると, 振動数は連続的になり, 場の量 \(f(t)\) は次のような「フーリエ変換」の関係式となる:
f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{\omega}\,e^{-i\omega t}\,\frac{d\omega}{2\pi},\quad
f_{\omega}=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,e^{i\omega t}\,dt
\tag{26}
\end{equation}
そして式 (25) に相当する式は次となる:
\int_{-\infty}^{\infty} f^{2}(t)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \big|f_{\omega}\big|^{2}\,\frac{d\omega}{2\pi}
=2\int_{0}^{\infty} \big|f_{\omega}\big|^{2}\,\frac{d\omega}{2\pi}
\tag{27}
\end{equation}
式 (25) の公式から, 振動数 \(\omega=n\omega_{0}\) の単色成分の強度は, 放射強度の式中の \(\ddot{\mb{d}}\) を, そのフーリエ成分 \(\ddot{\mb{d}}_{n}\) で置き換えることで求めることが出来る:
I=\frac{2}{3c^{3}}\,\overline{\ddot{\mb{d}}^{2}}\quad\rightarrow\quad
I_{n}=\frac{4}{3c^{3}}\,\big|\ddot{\mb{d}}_{n}\big|^{2}
\tag{28}
\end{equation}
ベクトル \(\ddot{\mb{d}}(t)\) のフーリエ成分は, ベクトル \(\mb{d}(t)\) のフーリエ成分で表される. そのため, \(\ddot{\mb{d}}(t)\) の展開の各成分は, \(\mb{d}(t)\) の展開の対応する成分の時間微分から得られることに注意する. すなわち,
\ddot{\mb{d}}_{\omega}\,e^{-i\omega t} =\frac{d^{2}}{dt^{2}}\big( \mb{d}_{\omega}\,e^{-i\omega t}\big)=-\omega^{2}\,\mb{d}_{\omega}\,e^{-i\omega t}
\tag{29}
\end{equation}
これより,
\ddot{\mb{d}}_{\omega}=-\omega^{2}\,\mb{d}_{\omega}
\tag{30}
\end{equation}
従って, 放射強度 \(I\) のフーリエ成分 \(I_{\omega}\) は次のように表される:
I_{\omega}=\frac{4}{3c^{3}}\,\big|\ddot{\mb{d}}_{\omega}\big|^{2}=\frac{4\omega^{4}}{3c^{3}}\,\big|\mb{d}_{\omega}\big|^{2}
\tag{31}
\end{equation}
このフーリエ積分への展開が必要となるのは, 荷電粒子の衝突の際に生じる放射, いわゆる「制動放射」(Bremsstrahlung) の場合である. そのときの全衝突時間に渡って放射されるエネルギーの総量を考えてみる. 振動数が \(\omega\) と \(\omega+d\omega\) の間にあるような波として放出されるエネルギーを \(d\mathscr{E}_{\omega}\) としよう. 式 (22) 及び式 (26) より, 放射の全エネルギー \(\Delta \mathscr{E}\) は次となる:
\Delta \mathscr{E}=\int_{-\infty}^{\infty} I\,dt=\frac{2}{3c^{3}}\int_{-\infty}^{\infty} \ddot{\mb{d}}^{2}\,dt
\tag{32}
\end{equation}
式(27)より, ここで積分を \(2|\ddot{\mb{d}}_{\omega}|^{2}\,d\omega/2\pi\) という表式に置き換えれば \(d\mathscr{E}_{\omega}\) の形にすることが出来る:
\Delta \mathscr{E}_{\omega}&=\int d\mathscr{E}_{\omega}=\frac{2}{3c^{3}}\int_{-\infty}^{\infty} \ddot{\mb{d}}^{2}\,dt
=\frac{2}{3c^{3}}\,2\int_{0}^{\infty}\left|\ddot{\mb{d}}_{\omega}\right|^{2}\,\frac{d\omega}{2\pi}
=\int_{0}^{\infty}\frac{2}{3\pi c^{3}}\big|\ddot{\mb{d}}_{\omega}\big|^{2}\,d\omega\notag\\
\rightarrow&\quad d\mathscr{E}_{\omega}=\frac{2}{3\pi c^{3}}\big|\ddot{\mb{d}}_{\omega}\big|^{2}\,d\omega
\tag{33}
\end{align}
放射減衰
運動する粒子による電磁波の放射は, 粒子のエネルギーの損失をもたらす. この損失の粒子の運動に及ぼす反作用は, 対抗する「摩擦力」 \(\mb{f}\) を運動方程式に導入することで記述される.
非相対論的な速度 (\(v\ll c\)) で定常運動を行っている電荷の系を考察する. 定常状態を考えることになるから, 入射するエネルギーと放射エネルギーは等しく,それは散逸エネルギーに一致すると考えられる. よって, 平均の損失は, 式 (28)の平均放射強度 \(I\) に等しい. このエネルギー損失が \(\mb{f}\) による仕事として与えられるように, この力 \(\mb{f}\) を選ぶことにする. 力 \(\mb{f}\) が単位時間にする仕事は, \(\mb{v}\) を粒子の速度として, \(\mb{f}\cdot\mb{v}\) に等しい. 従って,
\sum_{i} \overline{\mb{f}_{i}\cdot\mb{v}_{i}}=-\frac{2}{3c^{3}}\overline{\ddot{\mb{d}}^{2}}
\tag{34}
\end{equation}
でなければならない. ただし \(i\) についての和は粒子全部にわたる. また, マイナス符号はエネルギーは減少することを示すためである.
この要求を満たす力は次である:
\mb{f}_{i} = \frac{2q_{i}}{3c^{3}}\dddot{\mb{d}}
\tag{35}
\end{equation}
このことは, 実際に \(\sum_{i} \mb{f}_{i}\cdot\mb{v}_{i}\) にこの \(\mb{f}_{i}\) を代入して見ればよい:
\sum_{i} \mb{f}_{i}\cdot\mb{v}_{i}=\frac{2}{3 c^{3}}\dddot{\mb{d}}\sum_{i} q_{i}\mb{v}_{i}
=\frac{2}{3 c^{3}}\dddot{\mb{d}}\cdot\dot{\mb{d}}
=\frac{2}{3c^{3}}\frac{d}{dt}\big(\ddot{\mb{d}}\cdot\dot{\mb{d}}\big)-\frac{2}{3c^{3}}\,\ddot{\mb{d}}^{2}
\tag{36}
\end{equation}
が得られる. この平均をとると, 時間についての全微分である第1項はゼロになるため第2項目だけが残り, 結局は式 (34) になるからである. 式 (35) の力は,「放射減衰」或いは「ローレンツ摩擦力」と呼ばれている.
放射減衰は, 外場の中を運動する一個の電荷の場合にも起こる. このとき \(\dddot{\mb{d}}=e\ddot{\mb{v}}\) であるから, 式 (35) の放射減衰を「ローレンツ力」に付加した運動方程式は次の形になる:
m\dot{\mb{v}}=e\mb{E}+\frac{e}{c}\mb{v}\times\mb{H}+\frac{2q^{2}}{3c^{3}}\ddot{\mb{v}}
\tag{37}
\end{equation}
しかしながら, 減衰力を使って電荷のそれ自身への作用を記述することは一般に満足すべきものでなく, またそれは矛盾を含んでいることを忘れてはならない.
自由電荷による散乱
電磁波が電荷の系に出会うと, その作用の下で電荷は運動を始める. この電荷の運動が, 今度は全ての方向に放射を出す. このようにして, 元の波のいわゆる「散乱」が起こる.
散乱は, 散乱する系によって単位時間に与えられた方向へ放出されるエネルギー量と, 入射する放射のエネルギー流の密度との比によって特徴付けるのが最も便利である. この比は明らかに面積のディメンションを持ち「散乱断面積」と呼ばれる.
ポインティング・ベクトル \(\bf{S}\) を持って入射する波に対して, 単位時間に立体角 \(d\Omega\) 内へ系から放射されるエネルギーを \(dI\) としよう. このとき, 立体角 \(d\Omega\) への散乱の有効断面積は次である:
d\sigma = \frac{\overline{dI}}{\bf{S}}\quad\rightarrow\quad
\sigma=\frac{\overline{I}}{S}
\tag{38}
\end{equation}
ただし, 記号の上の横線は時間平均を意味する. 全ての方向について \(d\sigma\) を積分したもの \(\sigma\) は「散乱の全有効断面積」である.
静止している一つの自由電荷によって生じる散乱を考察しよう. この電荷に「直線偏光した単色平面波」が入射するとしよう. その電場は次の形に書くことが出来る:
\mb{E}=\mb{E}_{0}\,\cos\big(\omega\, t – \mb{k}\cdot\mb{r}+\alpha\big)
\tag{39}
\end{equation}
入射波の影響で電荷が得る速度は光速度に比べて小さいと仮定しよう. 実際にはほとんどいつもそうである. すると「ローレンツ力」のうちで, 電荷に働く力は \(e\mb{E}\) であると見做すことができ, 磁場による力 \(\displaystyle{\frac{e}{c}\mb{v}\times\mb{H}}\) は無視することが出来る. この場合, 場の作用によって電荷が振動するための電荷の変位の効果も無視することが出来る. 電荷が座標原点の周りで振動するものとすれば, 電荷に働く場は常に原点に於けるものと同じである. すなわち式 (39) で \(\mb{r}=0\) としたものと仮定することが出来る:
\mb{E}=\,\cos\big(\omega\, t +\alpha\big)
\tag{40}
\end{equation}
すると, 電荷の運動方程式は \( m\ddot{\mb{r}}=e\mb{E}\) であり, その双極子モーメントは \(\mb{d}=e\mb{r}\) であるから次式が得られる:
e\ddot{\mb{r}}=\ddot{\mb{d}}=\frac{e}{m}e\mb{E}\quad\rightarrow\quad \ddot{\mb{d}}=\frac{e^{2}}{m}\mb{E}
\tag{41}
\end{equation}
散乱された放射を計算するために, 式 (21) の「双極放射に対する公式」を利用する:
dI=\frac{1}{4\pi c^{3}}\big(\ddot{\mb{d}}\times\mb{n}\big)^{2}d\Omega=\frac{\ddot{\mb{d}}^{2}\sin^{2}\theta}{4\pi c^{3}}\,d\Omega
\tag{42}
\end{equation}
電荷が入射波の作用で得る速度は光速度に比べて小さいから, この公式を利用することは正当である. ここで \(\mb{n}\) は散乱波の進行方向の単位ベクトルである. また, 「電荷によって放射される ( すなわち, その電荷によって散乱される ) 波の振動数は明らかに入射波の振動数と同じである」ことに注意しておこう.
式 (42) に式 (41) を代入すると次が得られる:
dI=\frac{1}{4\pi c^{3}}\left(\frac{e^{2}}{m}\mb{E}\times\mb{n}\right)^{2}d\Omega
=\frac{e^{4}}{4\pi m^{2}c^{3}}\big(\mb{E}\times\mb{n}\big)^{2}\,d\Omega
=\frac{e^{4}}{4\pi m^{2}c^{3}}E^{2}\sin^{2}\theta\,d\Omega
\tag{43}
\end{equation}
ただし \(|\mb{E}\times\mb{n}|=E\sin\theta\) であって, 角度 \(\theta\) は, 散乱波の方向ベクトル \(\mb{n}\) と入射波の電場 \(\mb{E}\) の方向との間の角度である.
他方, 直線偏光した単色平面波である入射波の「ポインティング・ベクトル \(\mb{S}\)」は以下の手順で求めることが出来る. 平面波の場合には, 式 (11) より \(\mb{H}=\mb{n}\times\mb{E}\) が成り立ち, 平面波の電場 \(\mb{E}\) と磁場 \(\mb{H}\) とは波の伝搬方向に垂直に向いているため \(\mb{E}\cdot\mb{n}=0\) が成り立つ. また, 電場 \(\mb{E}\) と磁場 \(\mb{H}\) とは互いに直交し等しい大きさを持つことも言えた. すると, 次のベクトル解析の公式 $$\mb{A}\times(\mb{B}\times\mb{C})=(\mb{A}\cdot\mb{C})\mb{B}-(\mb{A}\cdot\mb{B})\mb{C}$$ を利用することで平面波の電場と磁場については次が言える:
\mb{E}\times\mb{H}=\mb{E}\times\big(\mb{n}\times\mb{E}\big)=\mb{E}\cdot\mb{E}\,\mb{n}-(\mb{E}\cdot\mb{n})\,\mb{E}=E^{2}\mb{n}
=H^{2}\mb{n}
\tag{44}
\end{equation}
すると, この場合のポインティング・ベクトルは次となる:
\mb{S}=\frac{c}{4\pi}\mb{E}\times\mb{H}=\frac{c}{4\pi}\mb{E}\times(\mb{n}\times\mb{E})=\frac{c}{4\pi}E^{2}\mb{n}=\frac{c}{4\pi}H^{2}\mb{n}
\tag{45}
\end{equation}
従って, 単位面積を単位時間に通過する入射波による場のエネルギーは次である:
S=\frac{c}{4\pi}E^{2}=\frac{c}{4\pi}H^{2}
\tag{46}
\end{equation}
以上の結果である式 (42) 及び式 (46) を式 (38) に代入すると, 立体角 \(d\Omega\) 内への散乱の有効断面積として次が得られる:
d\sigma =\frac{\overline{dI}}{S}=\frac{\ds{\frac{e^{4}}{4\pi m^{2}c^{3}}\big(E\sin\theta\big)^{2}\,d\Omega}}{\ds{\frac{c}{4\pi}E^{2}}}= \left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}\sin^{2}\theta\,d\Omega
\tag{47}
\end{equation}
これより, 自由電荷の散乱有効断面積は「振動数に無関係である」ことが分かる.
全有効断面積 \(\sigma\) を求めよう. そのために, 電荷の位置に原点を持ち, \(\mb{E}\) の方向に極軸を持つ極座標を導入する. そうすると \(d\Omega=\sin\theta\,d\theta\,d\phi\) である. これを代入し \(d\theta\) についてゼロから \(\pi\) まで, \(d\phi\) についてはゼロから \(2\pi\) まで積分すると次となる:
\sigma_{T}=\frac{\overline{I}}{S}=\int_{0}^{2\pi}d\phi\int_{0}^{\pi}\,\sin\theta\,d\theta\,\left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}\sin^{2}\theta
=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}=\frac{8}{3}\pi a_{0}^{2}
\tag{48}
\end{equation}
これは「Thomson 散乱の全断面積」または「 Thomson の公式」と呼ばれている. ただし \(a_{0}\) は「古典的電子半径」で, 次の大きさである:$$a_{0}=\frac{e^{2}}{mc^{2}}=2.8\times 10^{-13}\,\mathrm{cm}$$ すなわち, 古典的電子は半径 \(a_{0}\) の剛体球と考えることが出来る.
次に, 偏光していない波 (自然光) の散乱に対する散乱断面積 \(d\sigma’\) を求めておこう. 入射波の伝搬方向(波数ベクトル \(\mb{k}\) の方向) に垂直な平面内でベクトル \(\mb{E}\) のあらゆる方向について式 (11) を平均しなければならない. \(\mb{k}\) 方向に \(z\) 軸, \(\mb{E}\) 方向に \(x\) 軸を持つ座標系を導入しよう. そうすると, \(\mb{n}\) 及び \(\mb{E}\) の方向の間の角度の余弦, すなわち単位ベクトル \(\mb{n}\) の \(x\) 軸への射影は, \(\vartheta\) 及び \(\varphi\) を方向 \(\mb{n}\) の天頂角及び方位角としたとき, $$\cos\theta=\sin\vartheta\cos\varphi$$ である. \(\mb{k}\) に垂直な平面内の \(\mb{E}\) の全ての方向について平均することは, 方位角 \(\varphi\) について平均することと同等である. よって,
\overline{\sin^{2}\theta}&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\sin^{2}\theta\,d\varphi
=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\big(1-\cos^{2}\theta\big)\,d\varphi\notag\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}d\varphi-\frac{1}{2\pi}\sin^{2}\vartheta\int_{0}^{2\pi}\cos^{2}\varphi\,d\varphi
=\frac{1}{2\pi}\big(2\pi-\sin^{2}\vartheta\times\pi\big)\notag\\
&=1-\frac{\sin^{2}\vartheta}{2}=\frac{1+\cos^{2}\vartheta}{2}
\tag{49}
\end{align}
これを式 (47) に代入して, 次式が得られる:
d\sigma’ = \left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}\,\overline{\sin^{2}\theta}\,d\Omega= \frac{1}{2}\left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}\big(1+\cos^{2}\vartheta\big)\,d\Omega
\tag{50}
\end{equation}
調和振動子としての束縛電荷による散乱
今度は, 何らかの弾性力の作用によって角振動数 \(\omega_{0}\) で微小振動をしている電荷 (振動子) による直線偏光波の散乱断面積を求めてみよう. これは, 例えば Thomson の原子模型を考えていることに相当する. Thomson の原子模型は「半径 \(a\) の球の内部に正電荷が一様に分布し, その中に負電荷を持つ多数の点電子がスイカの種子のように分布している」とするものである.この模型によれば球内外の電場は球対称であって,
E(r)=\begin{cases} \ds{\frac{Ze}{a^{3}}r} & ( r < a ) \\ \ds{\frac{Ze}{r^{2}}} & ( r > a ) \end{cases}
\tag{51}
\end{equation}
となる.よってこの球内部の中心から \(r\) の距離だけズレた位置に電子があると, その電子に働く力 \(F\) は
F=-eE(r)=-\frac{Ze^{2}}{a^{3}}r\equiv -\frac{\omega_{0}}{m}\mb{r},\qquad \mb{F}_{L}=\frac{2e^{2}}{3c^{3}}\dddot{\mb{r}}
\tag{52}
\end{equation}
である.このとき質量 \(m\) の電子 \(-e\) に働く力として「ローレンツ減衰」 \(\mb{F}_{L}\) も考慮に入れよう (式 (37) を参照せよ).すると, 質量 \(m\) の電子の運動方程式は次となる:
m\ddot{\mb{r}}+m\omega_{0}^{2}\mb{r} = -e \mb{E}(t) + \frac{2e^{2}}{3c^{3}}\,\dddot{\mb{r}}
=-e \mb{E}(t) -\frac{2e^{2}}{3c^{3}}\omega_{0}^{2}\dot{\mb{r}}
\tag{53}
\end{equation}
ただし, ローレンツ減衰は, 近似的に \(\dddot{\mb{r}}=-\omega_{0}^{2}\dot{\mb{r}}\) と置けることを用いている.(これは「電荷を持った重い粒子が電子の付近を通過して電子に電磁波を与えるような状況」を考えていると思えば良い.このときローレンツ力 \(-e\mb{E}-e(\mb{v}/c)\times\mb{H}\) のうち, 磁場による力は非相対論的な場合では小さいとして無視できるから, 電子に作用するのはほぼ電場だけと考えて良い.その電場は重い粒子が飛び去ってしまうと無くなってしまう.従ってそれ以降の電子の運動は微小な摩擦力のある束縛電子の単振動となり, それは \(m\ddot{\mb{r}}=-m\omega_{0}^{2}\mb{r}+\mb{F}_{L}\) となる.ここで微小な力 \(\mb{F}_L\) を無視してしまえば \(m\ddot{\mb{r}}\approx -m\omega_{0}^{2}\mb{r}\) となり, この両辺を更に時間微分すれば \(\dddot{\mb{r}}=-\omega_{0}^{2}\dot{\mb{r}}\) を得る).すると運動方程式は, 次のような「強制振動の微分方程式」となる:
\ddot{\mb{r}}+\gamma\dot{\mb{r}}+\omega_{0}^{2}\mb{r} = \frac{-e}{m}\mb{E}(t),\quad\mathrm{where}\quad
\gamma=\frac{2e^{2}}{3mc^{3}}\omega_{0}^{2}
\tag{54}
\end{equation}
この強制振動に対する解を D.Jackson からの引用により求める手順を示して行こう.まず \(\mb{E}(t)\) と \(\mb{r}(t)\) のFourier変換を考える (工学と違って, 物理学では \(t\) と \(\omega\) の時には指数の符号を逆にした式とすることが多いので注意する):
\mb{r}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\mb{r}(\omega)e^{-i\omega t}\,d\omega,
\quad
\mb{E}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\mb{E}(\omega)e^{-i\omega t}\,d\omega
\tag{55}
\end{equation}
Fourier 変換の性質として, 関数 \(f(t)\) が \(t\to\pm\infty\) のとき \(f(t)\to0\) である場合, \(f(t)\) の微分 \(f'(t)\) のFourier変換 \(\mathcal{F}[f'(t)]\) は次となるのであった:
\mathcal{F}[f'(t)]=-i\omega F(\omega)=-i \omega \mathcal{F}[f(t)]
\tag{56}
\end{equation}
従って,
\dot{\mb{r}}(\omega)=-i\omega \mb{r}(\omega),\quad
\ddot{\mb{r}}(\omega)=-i\omega \dot{\mb{r}}(\omega)=(-i\omega)^{2}\mb{r}(\omega)=-\omega^{2}\mb{r}(\omega)
\tag{57}
\end{equation}
微分方程式 (54) の両辺を Fourier 変換したものに対して式 (57) を用いると,
-\omega^{2}\mb{r}(\omega)-i\omega\gamma\mb{r}(\omega)+\omega_{0}^{2}\mb{r}(\omega)=\frac{-e}{m}\mb{E}(\omega)
\tag{58}
\end{equation}
よって, 次が得られる:
\mb{r}(\omega)=\frac{-e}{m}\cdot \frac{\mb{E}(\omega)}{\omega_{0}^{2}-\omega^{2}-i\omega\gamma}
\tag{59}
\end{equation}
\(\mb{E}(t)\) の形が分かると Fourier 振幅 \(\mb{E}(\omega)\) が決定できるので, 上式 (59) と式 (55) から \(\mb{r}(t)\) が得られる.電荷が座標原点の周りで振動するものとすれば, 電子に働く場は常に原点に於けるものと同じとなる.よって, 例えば \(\mb{E}=\mb{E}_{0}e^{-i\omega t}\) とするならば, 次となる:
\mb{r}(t)=\frac{-e}{m}\frac{\mb{E}_{0}e^{-i\omega_{0}t}}{\omega^{2}_{0}-\omega^{2}-i\omega\gamma}
\tag{60}
\end{equation}
これから後の計算は前と同様に行うならば, 結局このときの散乱断面積は次となる:
\sigma_{R}=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^{2}}{mc^{2}}\right)^{2}\frac{\omega^{4}}{(\omega_{0}^{2}-\omega^{2})^{2}+\omega^{2}\gamma^{2}}
\tag{61}
\end{equation}
「特に入射波の角振動数が小さくて \(\omega_{0}\gg \omega\) のときには,
\sigma_{R}=\sigma_{T}\frac{\omega^{4}}{(\omega_{0}^{2}-\omega^{2})^{2}
+\omega^{2}\gamma^{2}}\simeq \sigma_{T}\frac{\omega^{4}}{\omega_{0}^{4}}
=\sigma_{T}\frac{\lambda_{0}^{4}}{\lambda^{4}}
\tag{62}
\end{equation}
となる. すなわち, 散乱断面積は入射波の波長の4乗に逆比例する. このような散乱は「Rayleigh 散乱」と呼ばれ, 電気双極子の特徴の一つである. 例えば, 空気分子による光波の散乱を考えると, 空気分子の大きさはおよそ 1Å 程度であり, 可視光の波長が数千Å の程度であることから, Rayleigh 散乱が起こり, 波長の短い青色の光の散乱される割合は赤色の光のそれよりも多くなるため, 空の色は青く見える 」.(砂川重信:「理論電磁気学」より).