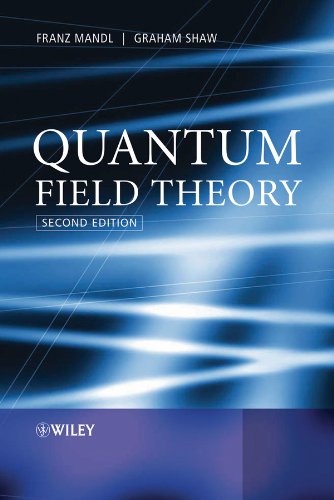場の量子論に於ける \(S\)-行列の議論の例として, F.Mandl, G.Shaw 著「Quantum Field Theory」の § 6.2 を翻訳したものを示す.

◎ このブログ記事をPDF化したものは次のリンクをクリックすることで見ることが出来る.またダウンロードボタンをクリックすることでダウンロードも可能である:
S-行列展開(The S-Matrix Expansion)
これまでは主に自由な場すなわち相互作用していない場を考察して来たが, そこでは状態ベクトルが時間的に一定で演算子が時間依存性を持つハイゼンベルグ描像(H.P.)を用いていた. 今度は, 相互作用する場の研究に目を向ける.例えば, 量子電気力学(QED)では, 相互作用する電子と陽電子そして電磁場は次のラグランジアン密度で記述される:
まず最初に,「相互作用描像」では, 演算子 \(O^{I}\) はハイゼンベルグ的な次の運動方程式
次に, 相互作用ラグランジアン密度 \(\mathscr{L}_I\) が微分を含まない場合(第19章まではこの場合に限定する), 相互作用のある場の正準共役は自由場の正準共役と同じである.(例えば QED では \(\partial \mathscr{L}/\partial\dot{\psi}_{\alpha}=\partial\mathscr{L}_0/\partial \dot{\psi}_{\alpha}\) など).相互作用描像とハイゼンベルグ描像はユニタリー変換によって関係づけられる.そのため相互作用描像では, 相互作用する場は自由場と同じ交換関係を満たすことになる.
このように相互作用表示では, 相互作用場は自由場の演算子と同じ運動方程式と同じ交換関係を満たしているのである.従って, 第3章から第5章までの自由場の結果は相互作用表示の相互作用場にも当てはまるものとして引き継ぐことが出来る.特に, 我々が得た平面波状態の完全系は運動方程式の解である.その結果, 以前と同じ平面波展開, 同じ数表示, 同じ明示的な式即ちファインマン伝搬関数となる.
相互作用表示に於いて, 系は時間依存する状態ベクトル \(\ket{\Phi(t)}\) で記述される.第1章の付録の式 (1.88) と式 (1.89):
式 (6.12) は時間依存するハミルトニアン \(H_I(t)\) を持ち, シュレディンガー方程式に類似した式である.相互作用を`スイッチオフ’する (即ち \(H_I\equiv0\) と置く) 場合, 状態ベクトルは時間的に一定である.相互作用は状態を時間変化する状態 \(\Phi(t)\) にする.系が初期時刻 \(t=t_i\) に状態 \(\ket{i}\) で与えられる, 即ち
ここで展開する理論形式は, 明らかに束縛状態の記述には適さないが, 散乱過程には特に適している.衝突過程では, 状態ベクトル \(\ket{i}\) は散乱が起こるずっと前 (\(t_i=-\infty\)) の初期状態を定義するが, それは相互作用しないように互いに離れた場所にあって明確な性質を持った粒子の明確な粒子数を指定することで定義される.(例えばQEDでは, 状態ベクトル \(\ket{i}\) は与えられたモーメント, スピン, 偏光を持った電子, 陽電子, 光子の明確な数を指定することになる).散乱過程では, 粒子は接近し衝突(すなわち相互作用)し, 再び飛び離れる.式 (6.12) が決定するのは散乱が終わって全ての粒子が再び離れた後の時刻 \(t =\infty\) に於いて, 初期状態 \(\ket{\Phi(-\infty)}=\ket{i}\) が時間発展した状態 \(\ket{\Phi(\infty)}\) である.\(S\)-行列は \(\ket{\Phi(\infty)}\) と \(\ket{\Phi(-\infty)}\) を関係付けるもので, 次式によって定義される:
衝突は様々な最終状態 \(\ket{f}\) を引き起こし, これらの可能性はすべて \(\ket{\Phi(\infty)}\) に含まれる.(例えば電子と陽電子の衝突は, 弾性散乱, 制動放射(すなわち光子の放出), 対消滅などをもたらすであろう).これらの最終状態 \(\ket{f}\) の各々は \(\ket{i}\) に類似した方法で指定される.
衝突の後 (即ち\(t=\infty\)で), 系が状態 \(\ket{f}\) に存在するという「遷移確率」は, 次式で与えられる:
もし状態 \(\ket{\Phi(\infty)}\) を, 状態の完全直交集合 \(\{\ket{f}\}\) で展開すると,
\(S\)-行列を計算するためには, 初期条件の式 (6.14a) が成り立つ場合の式 (6.12) を解く必要がある.これらの方程式は, 次の積分方程式にまとめることが出来る:
この方程式は反復的にしか解くことが出来ない.その結果得られる \(H_I\) の累乗としての摂動解は, 相互作用エネルギー \(H_I\) が小さい場合にのみ有効である.QEDの場合がそれであり, 光子と電子の相互作用を特徴づける無次元結合定数は「微細構造定数(fine structure constant)」\(\alpha\approx 1/137\) である.
反復法によって式 (6.21) を解くと, \begin{align*} \ket{\Phi(t)}=\ket{i}&+(-i)\int_{-\infty}^{t}dt_1\,H_I(t_1)\ket{i}\\ &+(-i)^{2}\int_{-\infty}^{t}dt_1 \int_{-\infty}^{t_1}dt_2\,H_I(t_1)H_I(t_2)\ket{\Phi(t_2)}, \end{align*} 等々となるので, 極限 \(t\to\infty\) で \(S\)-行列は以下のようになる:
特定の遷移 \(\ket{i}\to\ket{f}\) の振幅は \(\BraKet{f}{S}{i}\) で与えられることを見て来た.この行列要素に寄与する部分を展開式 (6.23) から選び出すのは複雑な問題で次の節で再び扱うことにするが, まずは初期状態 \(\ket{i}\) と最終状態 \(\ket{f}\) の指定について議論しなければならない.
上記の摂動公式では, 状態 \(\ket{i}\) と \(\ket{f}\) は, いつもの通りに, 摂動されていない自由場ハミルトニアン \(H_0\) の固有状態, つまり相互作用がオフになった状態 \(H_I=0\) である.私たちが扱っている粒子は, たとえ遠く離れていても実際の物理的な粒子であるため, この説明は間違っているように見える.電子は他の電子から遠く離れていても光子雲に囲まれている.それは本物の電子であり, 自分自身が作る電磁場を持たない裸の電子ではない.従って, 裸の粒子状態である \(\ket{i}\) と \(\ket{f}\) を使うには正当化が必要である.一つの方法として \(H_I(t)\) を \(H_I(t)f(t)\) に置き換えた「断熱仮説」(adiabatic hypothesis) に訴えることが考えられる.関数 \(f(t)\) は, 十分に長い区間 \(-T<t<T\) では \(f(t)=1\) であり, そして \(t\to \pm\infty\) につれて単調に \(f(t)\to0\) となるように選ぶ.[例えばQEDでは, 素電荷 \(e\) を時間依存する結合定数 \(ef(t)\) で置き換えることができる].このようにして, 初期状態と最終状態は「裸の粒子」によって記述される.区間 \(-\infty <t\le -T\) の間は \(H_I(t)\) を \(H_I(t)f(t)\) に置き換えた運動方程式 (6.12) が裸粒子から実際の物理的粒子を生成し, 区間 \(|t|\le T\) の間では物理的粒子と完全な相互作用 \(H_I(t)\) を扱っている事になる.特に, 完全な相互作用は区間 \(-\tau < t < \tau\) の間で有効である.その間, 粒子は相互作用するために十分に接近している(すなわち \(T \gg\tau\) としなければならない).断熱仮説の本質は「間隔 \(|t|<\tau\) の間に起こる散乱に於いては, 系の散乱前の長い時間 \((t\ll \tau)\) または散乱後の長い時間 \((t\gg \tau)\) での記述を信頼する(当てにする) ことは出来ない」ということである.極限 \(T\to\infty\) をとるのは計算の最後でだけである.もちろん, 最低次の摂動論で計算する(つまり式 (6.23) でゼロでない結果を与える最低次 \(n\) の項だけを使う)場合, 相互作用は遷移を起こすためだけに使われ, 裸の粒子を実際の粒子に変えるために使われるわけではない.この場合には, 計算の最初から極限 \(T\to\infty\) をとり, 完全な相互作用 \(H_I(t)\) を扱うことが出来る.
References
| ↑1 | 相互作用描像, そしてそのハイゼンベルグ描像やシュレーディンガー描像との関係については, 第1章の付録 (1.5節) で説明されている.この題材に精通していない読者は,この段階でその付録を深く勉強しておくことをお勧めする. |
|---|---|
| ↑2 | 【 参考メモ 】 日置善郎著「場の量子論」の§ I.7 に, およそ次のような文章があった: 「朝永-ディラック(相互作用)描像での相互作用ハミルトニアン \(H_I(t)\) について次の点を強調しておこう:ハミルトニアン密度は § I.3 に示されている式, \begin{align*} &\mathscr{H}(\pi(x),\phi(x),\partial_i\phi(x)) =\pi(x)\dot{\phi}(x)-\mathscr{L}(\phi(x),\partial_{\mu}\phi(x)),\tag{I.15}\\ &H=\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{H}(\pi(x),\phi(x),\partial_i\phi(x)) =\int d^{3}\mb{x}\,\pi(x)\dot{\phi}(x)-L ,\tag{I.16} \end{align*} からも分かるように, 場の演算子とその空間微分の関数(多項式)である. 従って \(H_I(t)\) は次の様に書ける: \begin{align*} H_I(t)&=e^{iH_0(t-t_0)} H_I e^{-iH_0(t-t_0)} =e^{iH_0(t-t_0)}\left(\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{H}\right)e^{-iH_0(t-t_0)}\\ &=\int d^{3}\mb{x}\,e^{iH_0(t-t_0)}\mathscr{H}(\pi(\mb{x},t_0),\phi(\mb{x},t_0),\partial_i\phi(\mb{x},t_0)) e^{-iH_0(t-t_0)}\\ &=\int d^{3}\mb{x}\,\mathscr{H}(\pi_T(\mb{x},t),\phi_T(\mb{x},t),\partial_i\phi_T(\mb{x},t)) \tag{I.97} \end{align*} ただし \(\phi_T\) は相互作用表示の場の演算子で, \begin{equation*} \phi_T(\mb{x},t)=e^{iH_0(t-t_0)}\phi_0(\mb{x}) e^{-iH_0(t-t_0)} \tag{I.89} \end{equation*} に従って時間発展する.また, この \(\phi_T(\mb{x},t)\) は自由なハイゼンベルグ場と同じ方程式に従う: \[i\pdiff{t}\phi_T(\mb{x},t)=[\phi_T(\mb{x},t),H_0]\] つまり \(H_I(t)\) は自由場のハイゼンベルグ演算子だけ表される.これはこの描像の非常に大きな利点と言える.自由場の平面波展開及び生成・消滅演算子が \(H_I(t)\) の中ではそのまま使えるからである」. また, § II.2 には次の様な文章もあった:「始めの時刻が \(t=-\infty\) で, 終りの時刻が \(t=+\infty\) と言っても, もちろん数学的な意味での無限大などではない.しかしながら, 反応はまさに一瞬のうちに起こるので, 実質的には非常に良い近似でこの様に扱うことが出来る」. |
| ↑3 | 一般的な場合, すなわち異なる時間の \(H_I(t_i)\) が互いに交換しない場合の時間発展演算子は次式のような「ダイソン級数」となる: \begin{align*} \mathscr{U}(t,t_0)&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-i}{\hbar}\right)^{n}\int_{t_0}^{t}dt_1\int_{t_0}^{t_1}dt_2\dotsb\int_{t_0}^{t_{n-1}}dt_n\,H_I(t_1)H_I(t_2)\dotsb H_I(t_n)\\
&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{-i}{\hbar}\right)^{n}\int_{t_0}^{t}dt_1\int_{t_0}^{t}dt_2\dotsb\int_{t_0}^{t}dt_n\,T\big\{H_I(t_1)H_I(t_2)\dotsb H_I(t_n)\big\}\\&\equiv T\,\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} dt’\,H_I(t’)\right]\end{align*}また, 日置によれば, 時間発展演算子は次のように表わすことも出来る: \begin{equation*}\mathscr{U}(t,t_0)=e^{iH_0(t-t_0)/\hbar}e^{-iH(t-t_0)/\hbar}\end{equation*} ただし,「一般的には \(H\) と \(H_0\) は可換ではないので\begin{equation*}e^{iH_0(t-t_0)/\hbar}e^{-iH(t-t_0)/\hbar}=e^{i(H_0-H)(t-t_0)/\hbar}=e^{-iH_I(t-t_0)/\hbar}\end{equation*} などとやってはいけない!」とのことである.この表現を用いると, ハミルトニアン \(H_0,\,H\)がエルミートであるならば時間発展演算子のユニタリー性は容易に示すことが出来る:\begin{equation*}\mathscr{U}^{\dagger}(t,t_0)\mathscr{U}(t,t_0)=e^{iH(t-t_0)/\hbar}e^{-iH_0(t-t_0)/\hbar}e^{iH_0(t-t_0)/\hbar}e^{-iH(t-t_0)/\hbar}=1\end{equation*} |
| ↑4 | [訳註] 式 (6.22a) と式 (6.22b) の2つの形式の等価性は, 例えば, 日置善郎著「場の量子論」の § II.4 に説明されている. |