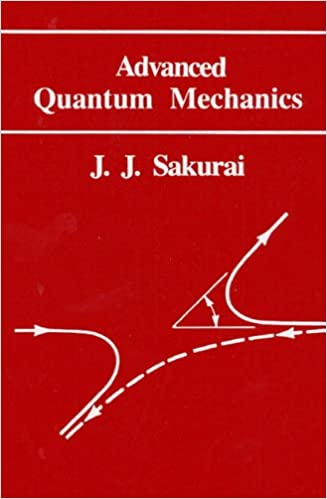\(\)
前の「自己エネルギー」に関連して「Lambシフト」の解説が J.J.Sakurai に書かれているので, それを引き続き記事として示しておく.
Dirac 理論によると, 水素原子の \(2S_{1/2}\) 準位と \(2P_{1/2}\) 準位は縮退していることになる.しかし W.Lamb と R.Retherford は実験により, それらに準位のずれがあることを示した.この「Lambシフト」と呼ばれるエネルギー準位のずれ(分裂) に理論的説明を最初に与えたのは H.Bethe の1947年の論文である[1] H.Bethe の1947年の論文は次のサイトから閲覧することが出来る:
http://www.physics.umd.edu/grt/taj/624a/Bethe1947.pdf
.J.J.Sakuraiは §2.8 で引き続き, この Bethe の論文に従って「Lambシフト」の計算方法を教科書的に丁寧に解説している.
Bethe の Lamb シフトの論じ方(Bethe’s treatment of the Lamb shift)
H.A.Bethe は, 精密な準位シフト測定が戦時中のマイクロ波技術開発によって可能となったことに刺激されて, 図2-7(b) に示した相互作用による水素原子のエネルギーシフトを計算する際に K.Kramers の「質量繰り込み」の考え方を応用した.式 (2.243) と式 (2.247) から, または式 (2.252) から次式が得られる(これらの図や式については前のブログ記事を見よ):
\begin{align}
\def\pdiff#1{\frac{\partial}{\partial #1}}
\def\reverse#1{\frac{1}{#1}}
\def\Bppdiff#1#2{\frac{\partial^{2} #1}{\partial #2^{2}}}
\def\ppdiff#1#2{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\def\BK#1#2{\langle #1 | #2 \rangle}
\def\BraKet#1#2#3{\langle #1 | #2 | #3 \rangle}
\def\ket#1{| #1 \rangle}
\def\bra#1{\langle #1 |}
\def\mb#1{\mathbf{#1}}
\def\ds#1{\mbox{${\displaystyle\strut #1}$}}
\Delta E_{A}^{\mathrm{(obs)}}&=\Delta E_A – C\BraKet{A}{\mb{p}^{2}}{A}\notag\\
&=\frac{2}{3\pi}\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{1}{(mc)^{2}}
\sum_I \int_{0}^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}\!\!\!\!\!\! \frac{E_{\gamma}\bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}}{E_A-E_I-E_{\gamma}}\,dE_{\gamma}
+\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2(\mb{p}^{2})_{AA}}{3\pi(mc)^{2}}
\int_{0}^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}\!\!\! dE_{\gamma}\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\int_0^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}
\left(\sum_{I}\frac{E_{\gamma}\bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}}{E_A-E_I-E_{\gamma}}+\sum_I\bigl|(\mb{p}^{2})_{IA}\bigr|^{2}
\right)\,dE_{\gamma}\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\int_0^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}
\sum_{I}\frac{\bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)}{E_A-E_I-E_{\gamma}}\,dE_{\gamma}\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_I-E_A)
\log\left(\frac{|E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}-E_A+E_I|}{|E_I-E_A|}\right)\notag\\
&\approx \left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_I-E_A)
\log\left(\frac{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}{|E_I-E_A|}\right)\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\log\left(
\frac{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}{\langle E_I-E_A\rangle_{\mathrm{average}}}\right)
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{I}-E_A),
\tag{2.253}
\end{align}
\def\pdiff#1{\frac{\partial}{\partial #1}}
\def\reverse#1{\frac{1}{#1}}
\def\Bppdiff#1#2{\frac{\partial^{2} #1}{\partial #2^{2}}}
\def\ppdiff#1#2{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\def\BK#1#2{\langle #1 | #2 \rangle}
\def\BraKet#1#2#3{\langle #1 | #2 | #3 \rangle}
\def\ket#1{| #1 \rangle}
\def\bra#1{\langle #1 |}
\def\mb#1{\mathbf{#1}}
\def\ds#1{\mbox{${\displaystyle\strut #1}$}}
\Delta E_{A}^{\mathrm{(obs)}}&=\Delta E_A – C\BraKet{A}{\mb{p}^{2}}{A}\notag\\
&=\frac{2}{3\pi}\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{1}{(mc)^{2}}
\sum_I \int_{0}^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}\!\!\!\!\!\! \frac{E_{\gamma}\bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}}{E_A-E_I-E_{\gamma}}\,dE_{\gamma}
+\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2(\mb{p}^{2})_{AA}}{3\pi(mc)^{2}}
\int_{0}^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}\!\!\! dE_{\gamma}\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\int_0^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}
\left(\sum_{I}\frac{E_{\gamma}\bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}}{E_A-E_I-E_{\gamma}}+\sum_I\bigl|(\mb{p}^{2})_{IA}\bigr|^{2}
\right)\,dE_{\gamma}\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\int_0^{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}
\sum_{I}\frac{\bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)}{E_A-E_I-E_{\gamma}}\,dE_{\gamma}\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_I-E_A)
\log\left(\frac{|E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}-E_A+E_I|}{|E_I-E_A|}\right)\notag\\
&\approx \left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_I-E_A)
\log\left(\frac{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}{|E_I-E_A|}\right)\notag\\
&=\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)\frac{2}{3\pi(mc)^{2}}\log\left(
\frac{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}{\langle E_I-E_A\rangle_{\mathrm{average}}}\right)
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{I}-E_A),
\tag{2.253}
\end{align}
ただし, 上式中では次の式変形を利用している:
\begin{align}
(\mb{p}^{2})_{AA}&=\BraKet{A}{(\mb{p}\cdot\mb{p})}{A}=\bra{A}\mb{p}\left(\sum_I\ket{I}\bra{I}\right)\mb{p}\ket{A}
=\sum_I \BraKet{A}{\mb{p}}{I}\BraKet{I}{\mb{p}}{A}=\sum_I(\mb{p})^{*}_{IA}(\mb{p})_{IA}\notag\\
&=\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}
\tag{2.254}
\end{align}
(\mb{p}^{2})_{AA}&=\BraKet{A}{(\mb{p}\cdot\mb{p})}{A}=\bra{A}\mb{p}\left(\sum_I\ket{I}\bra{I}\right)\mb{p}\ket{A}
=\sum_I \BraKet{A}{\mb{p}}{I}\BraKet{I}{\mb{p}}{A}=\sum_I(\mb{p})^{*}_{IA}(\mb{p})_{IA}\notag\\
&=\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}
\tag{2.254}
\end{align}
そして \(E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}\) は \(E_I-E_A\) よりもずっと大きいと仮定した.今やこの式 (2.253) の \(\Delta E_{A}^{\mathrm{(obs)}}\) は, \(E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}\) への依存性の敏感さがずっと少なくなっていることに注意する.我々のこの式は, 依然として \(E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}\to\infty\) のとき発散してしまうが, その発散は線形ではなく対数的である.
\(I\) についての和は, 次式が成り立つことに注意することで容易となる:
\begin{equation}
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)=-\frac{\hbar^{2}}{2}\int \bigl|\psi_A\bigr|^{2}\nabla^{2}V\,d^{3}x,
\tag{2.255}
\end{equation}
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)=-\frac{\hbar^{2}}{2}\int \bigl|\psi_A\bigr|^{2}\nabla^{2}V\,d^{3}x,
\tag{2.255}
\end{equation}
これが成り立つことは, 次の 3 ステップによって証明される.まず最初に, 無摂動ハミルトニアン \(H_0=\mb{p}^{2}/2m+V(\mb{x})\) に対して (演算子 \(\mb{p}=-i\hbar\nabla\) は \(H_0\) の後の要素にも作用すること及び \(H_0\) 中の \(V(\mb{x})\) だけに作用することから), 次式が成り立つことに注意する:
\begin{equation}
\mb{p}H_0 -H_0\mb{p}=\mb{p}V(\mb{x})+H_0\mb{p}-H_0\mb{p}=\mb{p}V(\mb{x})=-i\hbar\nabla V(\mb{x})
\tag{2.256}
\end{equation}
\mb{p}H_0 -H_0\mb{p}=\mb{p}V(\mb{x})+H_0\mb{p}-H_0\mb{p}=\mb{p}V(\mb{x})=-i\hbar\nabla V(\mb{x})
\tag{2.256}
\end{equation}
2番目に, 式 (2.256) の状態 \(I\) と状態 \(A\) 間の行列要素をとる:
\begin{align}
\BraKet{I}{\mb{p}H_0}{A}-\BraKet{I}{H_0\mb{p}}{A}&=E_A\BraKet{I}{\mb{p}}{A}-E_I\BraKet{I}{\mb{p}}{A}
=\mb{p}_{IA}E_A -E_I\mb{p}_{IA}\notag\\
&=\mb{p}_{IA}(E_A-E_I)=-i\hbar \left(\nabla V\right)_{IA}
\tag{2.257}
\end{align}
\BraKet{I}{\mb{p}H_0}{A}-\BraKet{I}{H_0\mb{p}}{A}&=E_A\BraKet{I}{\mb{p}}{A}-E_I\BraKet{I}{\mb{p}}{A}
=\mb{p}_{IA}E_A -E_I\mb{p}_{IA}\notag\\
&=\mb{p}_{IA}(E_A-E_I)=-i\hbar \left(\nabla V\right)_{IA}
\tag{2.257}
\end{align}
3番目は, 左から \(\mb{p}_{AI}=\mb{p}_{IA}^{*}\) を掛け合わせ, 和 \(I\) をとると,
\begin{equation}
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)=-\sum_I i\hbar \mb{p}_{AI}\cdot\left(\nabla V\right)_{IA}
\end{equation}
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)=-\sum_I i\hbar \mb{p}_{AI}\cdot\left(\nabla V\right)_{IA}
\end{equation}
その結果式は実数のはずであるから, 右辺量はその複素共役と等しいはずである:
\begin{align*}
&-i\hbar\sum_I \BraKet{A}{\mb{p}}{I}\BraKet{I}{\nabla V(\mb{x})}{A}
=-i\hbar\bra{A}\mb{p}\sum_I\ket{I}\bra{I}\nabla V(\mb{x})\ket{A}=-i\hbar\BraKet{A}{\mb{p}\nabla V(\mb{x})}{A}\\
&\quad =i\hbar\sum_I \BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})}{I}\BraKet{I}{\mb{p}}{A}
=i\hbar \bra{A}\nabla V(\mb{x})\sum_I \ket{I}\bra{I}\mb{p}\ket{A}=i\hbar\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}
\end{align*}
よって,
\begin{align}
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)&=-i\hbar\sum_I\mb{p}_{AI}\cdot\left(\nabla V\right)_{IA}
=i\hbar\sum_I \left(\nabla V\right)_{AI}\cdot\mb{p}_{IA}\notag\\
&=\frac{1}{2}\bigl\{-i\hbar\BraKet{A}{\mb{p}\nabla V(\mb{x})}{A}+i\hbar\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}\bigr\}\notag\\
&=-\frac{i\hbar}{2}\bigl\{\BraKet{A}{\mb{p}\nabla V(\mb{x})}{A}-\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}\bigr\}\notag\\
&=\frac{i\hbar}{2}\bigl\{\bra{A}(\mb{p}\cdot\nabla V+\nabla V\mb{p})\ket{A}-\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}\bigr\}\notag\\
&=\frac{i\hbar}{2}\BraKet{A}{\mb{p}\cdot\nabla V}{A}=\frac{i\hbar}{2}\BraKet{A}{-i\hbar\nabla\cdot\nabla V}{A}\notag\\
&=-\frac{\hbar^{2}}{2}\BraKet{A}{\nabla^{2}V}{A}
=-\frac{\hbar^{2}}{2}\bigl(\nabla^{2}V\bigr)_{AA}
\tag{2.258}
\end{align}
\sum_I \bigl|(\mb{p})_{IA}\bigr|^{2}(E_{A}-E_I)&=-i\hbar\sum_I\mb{p}_{AI}\cdot\left(\nabla V\right)_{IA}
=i\hbar\sum_I \left(\nabla V\right)_{AI}\cdot\mb{p}_{IA}\notag\\
&=\frac{1}{2}\bigl\{-i\hbar\BraKet{A}{\mb{p}\nabla V(\mb{x})}{A}+i\hbar\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}\bigr\}\notag\\
&=-\frac{i\hbar}{2}\bigl\{\BraKet{A}{\mb{p}\nabla V(\mb{x})}{A}-\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}\bigr\}\notag\\
&=\frac{i\hbar}{2}\bigl\{\bra{A}(\mb{p}\cdot\nabla V+\nabla V\mb{p})\ket{A}-\BraKet{A}{\nabla V(\mb{x})\mb{p}}{A}\bigr\}\notag\\
&=\frac{i\hbar}{2}\BraKet{A}{\mb{p}\cdot\nabla V}{A}=\frac{i\hbar}{2}\BraKet{A}{-i\hbar\nabla\cdot\nabla V}{A}\notag\\
&=-\frac{\hbar^{2}}{2}\BraKet{A}{\nabla^{2}V}{A}
=-\frac{\hbar^{2}}{2}\bigl(\nabla^{2}V\bigr)_{AA}
\tag{2.258}
\end{align}
となり, 式 (2.255) が得られる.水素原子の場合 \(\displaystyle V=-\frac{e^{2}}{r}\) であるから次である:[2][訳註] 電磁気学の公式から, \begin{equation*} \mathrm{div}\,\mb{E}=4\pi\rho,\qquad \mb{E}=-\nabla \phi, \end{equation*} この2つの式から電場 \(\mb{E}\) … Continue reading
\begin{equation}
\nabla^{2}V = 4\pi e^{2}\,\delta^{(3)}(\mb{x})
\tag{2.259}
\end{equation}
\nabla^{2}V = 4\pi e^{2}\,\delta^{(3)}(\mb{x})
\tag{2.259}
\end{equation}
また, 原子の波動関数は \(s\) 状態を除いて原点で消失することを思い出そう.式 (2.255) に現れる積分は [3][訳註] L.Pauling & E.Wilson:Quantum Mechanics の § 21a の表 21-4 によれば, 水素様原子の波動関数は \(\sigma=Zr/a_0\) … Continue reading,
\begin{equation}
\bigl(\nabla^{2}V\bigr)_{AA}=\int |\psi_A|^{2}\,\nabla^{2}V\,d^{3}x=4\pi e^{2}|\psi_A(0)|^{2}
=\begin{cases} \ds{\frac{4 e^{2}}{n^{3}a_0^{3}}} &
\mathrm{for}\ s\ \mathrm{states},\\ 0 & \mathrm{others},\end{cases}
\tag{2.260}
\end{equation}
\bigl(\nabla^{2}V\bigr)_{AA}=\int |\psi_A|^{2}\,\nabla^{2}V\,d^{3}x=4\pi e^{2}|\psi_A(0)|^{2}
=\begin{cases} \ds{\frac{4 e^{2}}{n^{3}a_0^{3}}} &
\mathrm{for}\ s\ \mathrm{states},\\ 0 & \mathrm{others},\end{cases}
\tag{2.260}
\end{equation}
ただし, \(a_0\) は水素原子の「Bohr半径」である:
\begin{equation}
a_0 = \frac{\hbar/mc}{e^{2}/\hbar c}=\frac{\hbar^{2}}{me^{2}}
\tag{2.261}
\end{equation}
a_0 = \frac{\hbar/mc}{e^{2}/\hbar c}=\frac{\hbar^{2}}{me^{2}}
\tag{2.261}
\end{equation}
すると \(s\) 状態の観測可能な準位シフトは今や次となる:
\begin{equation}
\Delta E_{A}^{\mathrm{(obs)}}=\frac{8}{3\pi}\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)^{3}\left(\frac{e^{2}}{2a_0}\right)
\frac{1}{n^{3}}\log\left(\frac{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}{\langle E_I-E_A\rangle_{\mathrm{ave}}}\right)
\tag{2.262}
\end{equation}
\Delta E_{A}^{\mathrm{(obs)}}=\frac{8}{3\pi}\left(\frac{e^{2}}{\hbar c}\right)^{3}\left(\frac{e^{2}}{2a_0}\right)
\frac{1}{n^{3}}\log\left(\frac{E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}}{\langle E_I-E_A\rangle_{\mathrm{ave}}}\right)
\tag{2.262}
\end{equation}
ただし \(e^{2}/2a_0=me^{4}/2\hbar^{2}\) は, 水素原子の基底状態に対するイオン化エネルギーである(「リュードベリ エネルギー」\(Ry\) と表記されることもある [4][訳註] (ランダウ:「量子力学」§31より) クーロン場に関連した計算を行うときには, … Continue reading ) ことを思い出して欲しい.\(l\ne0\) 状態の場合, 観測可能な準位シフトは期待できない.
シュレディンガー理論では, 水素原子のエネルギー準位は主量子数 \(n\) にのみ依存することがよく知られている.第3章で述べるように, ディラック方程式を用いて水素原子問題を解くと, 上記の縮退は「スピン-軌道(相互作用)力」によって部分的に取り除かれるが, 同じ \(n\) と \(j\) を持つ状態は依然として縮退している.特に \(2S_{1/2}\) 状態と \(2P_{1/2}\) 状態は, ディラック理論によれば完全に縮退している [5][訳註] 水素原子の基底状態は \(n=1,l=0,s=1/2\) に対応し, その結果全角運動量量子数 \(j=l+s=1/2\) となり, これの分光学的表示は \(1S_{1/2}\) … Continue reading.\(2S_{1/2}\) 状態と \(2P_{1/2}\) 状態状態の間にエネルギー差が存在する可能性は 1940 年代以前から S.Pasternack らによって推測されていたが, 戦時中にマイクロ波技術が開発されるまでこのエネルギー差を正確に測定することは出来なかった.1947年に W.E.Lamb と R.C.Retherford は \(2S_{1/2}-2P_{1/2}\) 分離に対応するラジオ波の周波数は約 \(1060\) Mc であり \(2S\) 状態の方が高いことを示した [6]ラムシフトの大きさを理解するためには, 基底状態のイオン化エネルギー \(1E^{1}=13.6\mathrm{eV}=2.18\times10^{-11}\mathrm{erg}\) に相当する周波数は … Continue reading.
Bethe は Lamb と Retherford の観測を説明するために式 (2.262) を導き出した.\(2S\) 状態の平均励起エネルギー \(\langle E_I-E_A\rangle_{\mathrm{ave}}\) はリュードベリエネルギーの 17.8 倍と数値計算で推定され,(相対論的領域でのアプローチ全体の破綻を考慮に入れて) \(E_{\gamma}^{\mathrm{(max)}}\) を \(mc^2\) とすると, 計算された \(2S\) 状態の上方へのシフトは \(1040\) Mc となり, 観測結果と驚くほど一致した.
§ 4-7 で述べるが, その後の相対論的な計算により, この分離値は完全に収束した値となっている [7]この理由は V. F. Weisskopf が最初に示したように, … Continue reading.理論値 \(1057.7\pm 0.2\) Mc は実験値 \(1057.8\pm 0.1\) Mc に匹敵している [8]R.T.Robiscoe による最近の「Lambシフト」は \(1058.05\pm 0.10\) Mc である.この値は, 現今の理論値 \(1057.50\pm 0.11\) Mc と幾分かの差がある.現時点では, … Continue reading.いずれにせよ, ベーテの半定量的な論じ方の成功は,「Lambシフト」が基本的には非相対論的な低周波的効果であることを示している.さらに重要なことは, 現在の場の理論に内在する発散の困難さにもかかわらず, 観測と比較可能な微妙な数値をどのようにして抽出できるかをこの論法が示していることである.Bethe の計算を成功させるための基本である「質量の繰り込み」の考え方は,「Lambシフト」のより洗練された相対論的な扱いに於いても同様に重要な役割を果たすことが分かった.
References
| ↑1 | H.Bethe の1947年の論文は次のサイトから閲覧することが出来る: http://www.physics.umd.edu/grt/taj/624a/Bethe1947.pdf |
|---|---|
| ↑2 | [訳註] 電磁気学の公式から, \begin{equation*} \mathrm{div}\,\mb{E}=4\pi\rho,\qquad \mb{E}=-\nabla \phi, \end{equation*} この2つの式から電場 \(\mb{E}\) を消去すると, \begin{equation*} \mathrm{div}\,\mb{E}=\nabla\cdot(-\nabla \phi)=-\nabla^{2}\phi =4\pi\rho,\quad\rightarrow\quad \nabla^{2}\phi =-4\pi\rho \end{equation*} 水素原子の電荷密度は \(\rho=e\delta^{(3)}(\mb{x})\) であり, 電子のポテンシャルエネルギーは \(V=-e\phi\) であるから, \begin{equation*} \nabla^{2}V=-e\nabla^{2}\phi = -e\times (-4\pi)e\,\delta^{(3)}(\mb{x})=4\pi e^{2}\,\delta^{(3)}(\mb{x}) \end{equation*} |
| ↑3 | [訳註] L.Pauling & E.Wilson:Quantum Mechanics の § 21a の表 21-4 によれば, 水素様原子の波動関数は \(\sigma=Zr/a_0\) として次である: \begin{align*} \psi_{1s}(\sigma)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}e^{-\sigma}\quad&\rightarrow\quad |\psi_{1s}(0)|^{2}=\frac{1}{\pi}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3},\\ \psi_{2s}(\sigma)=\frac{1}{4\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}(2-\sigma)e^{-\sigma/2}\quad&\rightarrow\quad |\psi_{2s}(0)|^{2}=\frac{1}{8\pi}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3},\\ \psi_{3s}(\sigma)=\frac{1}{81\sqrt{3\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}(27-18\sigma+2\sigma^{2})e^{-\sigma/3}\quad&\rightarrow\quad |\psi_{3s}(0)|^{2}=\frac{1}{27\pi}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3},\\ \rightarrow \quad 4\pi e^{2}|\psi_{ns}(0)|^{2}=4\pi e^{2}\frac{1}{n^{3}\pi}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3}_{Z=1} &=\frac{4e^{2}}{n^{3}a_0^{3}} \end{align*} |
| ↑4 | [訳註] (ランダウ:「量子力学」§31より) クーロン場に関連した計算を行うときには, 全ての量を測るのに,「原子単位」と呼ばれる特別な単位を用いると便利である.すなわち質量, 長さおよび時間を測る単位として, それぞれ次のものを選ぶ: \begin{equation*} m=9.11\times 10^{-28}\,\mathrm{g},\quad a_0=\hbar^{2}/me^{2}=0.529\times 10^{-8}\,\mathrm{cm}, \quad \hbar^{3}/me^{4}=2.42\times 10^{-17}\,\mathrm{sec} \end{equation*} ただし \(m\) は電子の質量である.長さの原子単位 \(a_0\) は「ボーア半径」と呼ばれる.これ以外の全ての単位はこれらから導くことが出来る.例えば, エネルギーの単位は「ハートリーエネルギー」\(E_h\) と呼ばれ, \begin{equation*} E_h=me^{4}/\hbar^{2}=2\mathrm{Ry}=4.36\times 10^{-11}\,\mathrm{erg}=27.21\,\mathrm{eV} \end{equation*} となる.Ry\(=me^{4}/2\hbar^{2}\) は「リドベリ」と呼ばれる.電荷の原子単位は素電荷 \(e=4.80\times10^{-10}\,\mathrm{erg}\) 静電単位である.原子単位の式へ移行するには式の中で \(e=1,m=1,\hbar=1\) と置けば良い. |
| ↑5 | [訳註] 水素原子の基底状態は \(n=1,l=0,s=1/2\) に対応し, その結果全角運動量量子数 \(j=l+s=1/2\) となり, これの分光学的表示は \(1S_{1/2}\) となる.第1励起準位に対しては \(n=2\) で, この場合 \(l=0\) か \(l=1\) である.\(n=2,l=1,s=1/2\) の場合には \(j=3/2\) か \(j=1/2\) となり, 2種の状態 \(2P_{3/2}\) と \(2P_{1/2}\) が生じる. |
| ↑6 | ラムシフトの大きさを理解するためには, 基底状態のイオン化エネルギー \(1E^{1}=13.6\mathrm{eV}=2.18\times10^{-11}\mathrm{erg}\) に相当する周波数は \(\nu=1E^{1}/h=3.29\times10^{9}\,\mathrm{MHz}\) でその逆波長(エネルギー \(E=hc/\lambda\) であるから逆波長 \(\lambda^{-1}\) はエネルギーの大きさを表わす) が \(\lambda^{-1}=1.1\times10^{5}\,\mathrm{cm}^{-1}\) (波長は \(\lambda=9.12\times10^{-6}\,\mathrm{cm}\)) であるのに比べて, 周波数 \(1060\) MHz に対応する逆波長が \(\lambda^{-1}=0.035\,\mathrm{cm}^{-1}\) (波長は \(\lambda=28.6\,\mathrm{cm}\)) であること, すなわち「Lambシフトの大きさはイオン化エネルギーのおよそ1000万分の1である」ことに注意する. |
| ↑7 | この理由は V. F. Weisskopf が最初に示したように, 相対論的な取り扱いでは自由電子または束縛電子の自己エネルギーが対数的にしか発散しないからである.乱暴に言えば, 式 (2.253) の2つの線形に発散する式の差は対数的にしか発散しないのと同じように, 相対論的アプローチで現れる 2 つの対数的に発散する式の差は有限であることが分かる. |
| ↑8 | R.T.Robiscoe による最近の「Lambシフト」は \(1058.05\pm 0.10\) Mc である.この値は, 現今の理論値 \(1057.50\pm 0.11\) Mc と幾分かの差がある.現時点では, このわずかな食い違いが量子電磁力学の破綻を示す証拠となり得るかどうかは不明である. |